プロジェクトセカイ(プロセカ)は、日々多くの楽曲と譜面が追加されており、それに伴って難易度の見直しや改定も定期的に行われています。
特に、プロセカの難易度で検索する方にとっては、各楽曲の難しさをどう読み取るかが重要な情報です。
本記事では、過去に行われた難易度の変更やmaster・append譜面の特徴、さらには30・31・32・37といった高難易度帯の傾向まで詳しく解説します。
また、難易度に関するランキングや一覧の「表」形式での整理、プレイヤーが「勝手に」感じる体感とのズレ、「報酬」やイベントとの関連性など、多角的な視点で分析しています。
難易度の読み方に迷ったときや、隠すように変化していく表記の背景を知りたいときに、ぜひ参考にしてください。
■本記事のポイント
- 難易度表記の変更や改定の歴史
- masterやappend譜面の特徴と違い
- 難易度ランキングや一覧の見方
- 難易度と譜面傾向・報酬との関係
プロセカで難易度の最新変動と一覧情報
プロジェクトセカイ(プロセカ)では、楽曲追加や譜面の進化に合わせて、難易度の見直しや表記変更が定期的に行われています。
プレイヤーにとっては、挑戦する楽曲の難しさが大きく影響するため、これらの変更は見逃せない情報です。
ここでは、過去に行われた難易度変更の歴史や、実際に変更された楽曲の一覧を「表」で分かりやすく整理し、さらに譜面のタイプ別にどのような傾向があるのかを詳しく解説していきます。
難易度の変更の歴史と一覧まとめ
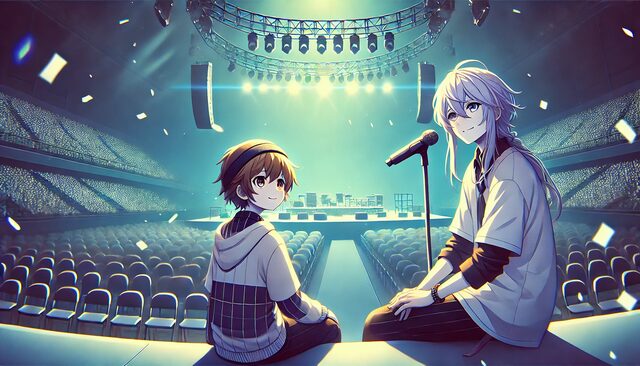
現在のところ、プロセカではこれまで難易度表記(難易度レベル)の変更が3回行われています。
譜面内容は変わらず、表記修正が中心です。
その背景としては、楽曲が増えるにつれ難易度表が実態とずれてしまうことが挙げられます。
それでは、変更の内容を時系列で見ていきましょう。
まず、2021年9月26日に最初の大規模見直しが行われました。
例えば「チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!」のMASTER難易度は30から31に、「千本桜」はMASTERで31→32、EXPERTでは25→26へと引き上げられています。
また「ジャンキーナイトタウンオーケストラ」もMASTER難易度が30→31に変更されました。
次に、2022年3月25日には高難度帯を中心にさらなる調整が行われ、高難易度層の表現幅を広げる目的がありました。
例えば「the EmpErroR」や「Don’t Fight The Music」はMASTERで34→36に、「初音ミクの消失」はMASTERで33→35に引き上げられています。
難易度調整はEXPERTやHARD譜面にも波及しています。
その後、2023年12月28日にも改定が実施され、APPEND譜面やトレースノーツの導入が背景にあった難易度見直しが行われました。
これら変更は楽曲ごとにまとめられた一覧で確認できますが、未記載のものも含めて随時更新が必要です。
以上により、難易度表記は時とともに調整されており、実際の譜面難易度とユーザー認識の齟齬を減らすための運営側の努力が見えてきます。
全楽曲難易度ランキングで見る

プロセカに収録されている楽曲は、「クリア」「フルコンボ」「ALL Perfect(AP)」という3段階で評価されており、それぞれの達成難易度がランキング形式で整理されています―例えばクリア難易度AからCのように分類され、譜面傾向や難所の特徴も併記されています。
たとえばレベル30以上の難易度帯では、「エンヴィキャットウォーク」はクリア・フルコン・APすべてA評価で、BPM変化や物量譜面の傾向があります。
一方「庭師のおはなしによると」はクリア:B、フルコン:B、AP:Aと少し癖があり、小粒配置や認識難、フリック難が特徴です。
「APPEND」譜面についても同様に評価されていて、「フラジール」は階段配置、「トワイライトライト」はスライド難・リズム難の傾向などが明記されています。
このような難易度ランキングは、譜面タイプの具体的傾向と自分の得意/不得意に応じて選曲できる点が大きなメリットです。
ただし、すべての評価がプレイヤーの主観に依存する面もあるため、試しプレイで確認することも重要です。
「表」で整理する難易度の見直し結果

ただ、プロセカでは楽曲の譜面自体を変えずに、難易度レベル表記のみを修正する見直しが複数回行われています。
そのため、変更された楽曲と旧/新の難易度を一覧形式で把握できる表が非常に役に立ちます。
こうした表は、楽曲追加や難易度増加に伴って起こる誤差を修正し、実際の譜面と表記の整合性を保つために必要です。
たとえば、ある記事では「過去に難易度表記が変更された楽曲を一覧表としてまとめています」と明記されており、2025年6月に4回目の見直しまで行われたことが確認できます。
こうすれば、どの曲のLVがどのタイミングでどのように変わったかがひと目でわかり、プレイヤーが選曲する際の目安になります。
ただし、こうした表は非公式で個人がまとめたものであることが多く、完全な網羅や公式保証がない点は注意が必要です。
それでも参照する価値は高く、自ら表形式にまとめて管理するのもおすすめです。
「譜面」タイプ別に見る度傾向
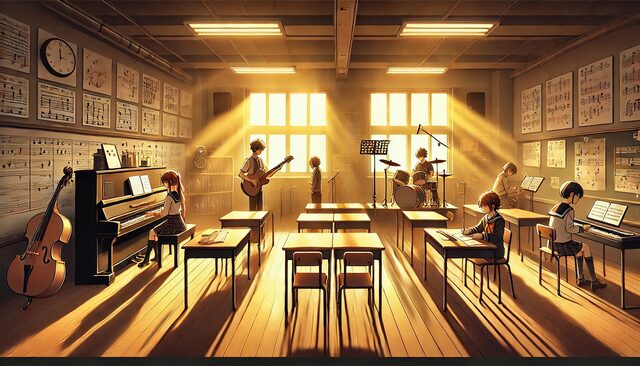
一方で、譜面の特徴別に難易度傾向を整理することも非常に有効です。
具体的には「物量×認識難」「テクニック全振り」「フリック・スライド難」など、譜面の性質に応じた分類があります。
たとえばレベル32帯では「インビジブル」が「物量×認識難譜面」として、後半の見づらさと複雑な配置によって攻略の難易度が上がる譜面として紹介されていま。
一方、レベル31帯には「脱法ロック」のように「テクニック全振り譜面」とされ、癖の強い配置や複雑な運指を要することが特徴とされています。
このように譜面タイプごとに傾向をつかむと、プレイヤーは自分が得意な譜面や苦手なタイプを把握でき、効率よく上達も目指せるようになります。
ただし機械的に分類するだけでは対応しきれない個別の癖や例外も存在するため、最終的には自分でプレイして感触を確かめることが大切です。
プロセカの難易度マスター/APPEND等の見方と読み方

プロセカでは、楽曲ごとに設定されている難易度がプレイ体験を大きく左右します。
特に「MASTER」や「APPEND」といった高難易度譜面は、見た目以上に複雑で、正しく読み解くには事前の知識が欠かせません。
ここでは、それぞれの難易度表記がどういう意味を持つのか、プレイスタイルにどのような影響を与えるのかを詳しく解説していきます。
また、APPEND特有のプレイ方法や、難易度の読み違いを防ぐための注意点についても触れていきます。
master・appendとは?

プロセカでは、難易度「MASTER」と「APPEND」が存在し、それぞれ異なる設計思想のもとに用意されています。
MASTERは従来の最高難易度で、レベル26~37をカバーし、主に2本指でも対応可能な譜面構成です。
一方、APPENDは3周年アップデートに追加された新難易度で、3本指以上でのプレイを前提に設計されており、PLAY体験にさらなる挑戦をもたらします。
そのため、APPENDは単にMASTERより難しいというよりも、多本指ならではの配置やリズムが増え、プレイヤースキルの幅を広げる意図があります。
両者の違いを理解して選曲すれば、より自分に合った楽しみ方が見えてきます。
「append」譜面に必要な多本指プレイと難易度

APPEND譜面は、3本指以上の多本指プレイが前提とされていることが最大の特徴です。
そのため、2本指プレイヤーにとってはかなり難しい配置に感じられるかもしれません。
具体的には、複数箇所を同時に押す「多点押し」や、高速なフリック・スライド配置が多く混在するため、指をそれぞれ独立して動かせる技術が求められます。
初心者の方には、本来の難易度だけでなく運指の負荷も重みがあります。
そのため、まずはHARD譜面を意識的に多本指で練習したり、他の音ゲーで慣れてから挑戦するのが効果的です。
こうした準備を経た結果、APPEND譜面にも対応できるようになれば、確実にリズムゲームの次のステージへと進めるようになります。
難易度の読み方のポイントと注意点

プロセカの難易度表記は「EASY」「NORMAL」「HARD」「EXPERT」「MASTER」「APPEND」の6段階に分かれています。
APPENDは「アペンド」と読み、2023年9月30日に追加された新しい難易度です。
各難易度にはレベル範囲が設定されており、APPENDはLv23から38、MASTERはLv26から37という構成です。
これらの読み方やレベル範囲を理解しておくと、自分の実力に応じた譜面選びがしやすくなります。
ただし、難易度表記だけで譜面の難しさを判断するのは避けたほうがよいでしょう。
たとえば、同じMASTER譜面でも譜面傾向やノーツ配置のクセによって、体感難易度に大きな差が出ることがあります。
そのため、表記だけで決めず、譜面傾向も確認して選ぶのが賢明です。
また、APPENDは多本指前提設計なので、読み方や運指環境を整えてから挑むのがおすすめです。
「勝手に」感じる難易度?体感とのズレと見直し
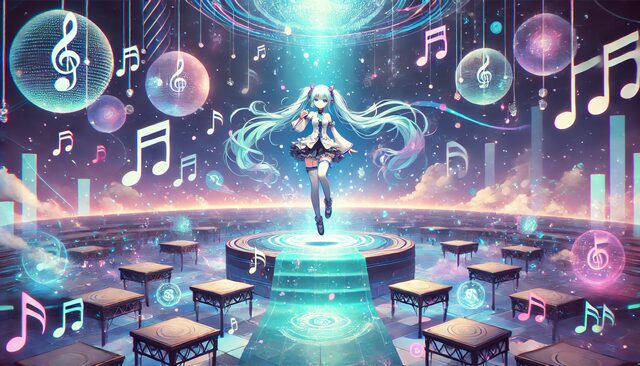
プロセカでは、公式の難易度レベルとプレイヤーが実際にプレイしたときの「体感難易度」が一致しないことがあります。
たとえば、ノーツ密度や認識難が高い譜面はレベル表記に見合わないほど難しく感じられることがあります。
また、逆に表記以上にサクサクとクリアできてしまう譜面もあるため、印象に大きな差が生じやすいです。
このようなズレを感じた場合は、譜面傾向や配置の特徴を確認し、自分が苦手な要素を把握することが大切です。
体感難易度が高く感じる場合、同じレベル帯でも癖が少ない譜面を優先すると、上達のスピードも上がります。
ただし、すべての情報を網羅できるわけではない点は注意が必要です。
あくまで目安として、自分の手で実際にプレイして「本当に難しいかどうか」を確かめてみましょう。
高難易度(30から32、37)譜面の特徴まとめ

30から32、37といった高難易度帯は、レベル数に加えて譜面の傾向が幅広く、個人差が極めて大きい点が特徴です。
たとえば、30の代表的な譜面では「エンヴィキャットウォーク」が配置難として認識され、縦連やテンポ変化が曲中で厄介さを増しています。
認識への慣れが攻略の鍵となります。
また、32帯ではアンケートによってランク付けされたランキング結果があり、MASTER譜面の傾向として、曲によって個人差が大きく分かれる点が興味深い事実として挙げられています。
とくにAPPEND譜面には、難易度に比して極端に難しい楽曲も混在しており、レベル表記だけでは難易度を測りきれない実態が見て取れます。
これら高難易度譜面では、物量、配置のクセ、リズムの複雑さなど、多種多様な要素が絡み合うため、自分の得意・不得意を見極めたうえで譜面選びすると効果的です。
難易度アップ/改定されやすい楽曲の傾向とは?

楽曲の難易度表記は、プレイヤーの認識とのズレを埋めるため、修正(改定)が行われることがある点が重要です。
この改定は、リリース当初の表記が譜面内容やプレイヤーの体感と乖離してしまった場合に、より妥当なレベルに再設定する目的で実施されます。
傾向としては、MASTER譜面の中でも特に人気曲や物量譜面、認識難が強い譜面ほど表記変更の対象になりやすいようです。
過去の改定例では、「千本桜」や「チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!」などがLvの変更を受け、より正確な難易度帯に修正されています。
そのため、改定履歴を定期的に確認することで、選曲時に混乱を避けることができます。
プレイヤー自身も新旧表記の違いを把握しておくと、より納得感のあるプレイが可能になるでしょう。
「報酬」やイベントと難易度の改定の関連性は?

プロセカでは、曲の難易度自体によってライブ報酬やイベントポイント(P)が直接変動するわけではないものの、難易度が高いほど得られるスコアが上がりやすいため、結果として報酬に反映されるケースがあります。
スコアが高いとイベントPや経験値が増加し、報酬効率にもつながりやすいのです。
イベントにおいては、イベントポイントやバッジ獲得でランキング報酬・称号・交換所アイテムなどが得られる仕組みになっており、難易度の区分とは別に、報酬設計が組まれています。
そのため、難易度改定によって表記が上がると「この譜面で高スコアを狙いたい」といった意欲が刺激される一方で、報酬との直接の関係は薄いため、表記変動が報酬バランスに影響することはあまり考えにくいのが現状です。
【まとめ】プロセカの難易度について
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


