メタファーの難易度について調べている方に向けて、リファンタジオの各モードの違いやキングオブキングスへの挑戦基準、おすすめの進め方を整理します。
物語と育成を両立させたい人にも、トロフィー集めやトロコンを狙う人にも役立つよう、メリットとデメリットを踏まえた攻略の考え方を解説します。
序盤から終盤までのキング戦やハード寄りの調整に対応する実践的な視点を示し、2週目以降に生まれる選択の幅、経験値の活かし方、難易度の変更可否、高い壁を乗り越える手順までを網羅します。
■本記事のポイント
- 各難易度の特徴と変更可否の全体像
- おすすめの選び方と進行中に見直す基準
- ハードやキングオブキングスへの準備と対策
- トロフィーとトロコンに向けた周回計画
メタファーで難易度の基本理解と特徴
メタファー:リファンタジオの魅力は、物語をじっくり味わいたいプレイヤーから腕試しを求める上級者まで幅広く満足させる、多彩な難易度設計にあります。
しかし、その選び方や違いを正しく理解していないと、思わぬ詰まりや後悔につながることも少なくありません。
本セクションでは、各難易度の特徴や変更の可否、最高難易度「キングオブキングス」に挑む際の留意点までを体系的に整理します。
さらに、目的別のおすすめ設定やトロフィー取得を見据えた戦略も解説し、これからプレイを始める人も周回を重ねる人も、最適な難易度選択ができるようサポートします。
リファンタジオを題材にした難易度解説

物語を主導したい人から腕試しを望む人まで、メタファー:リファンタジオは複数段階の難易度を用意しています。
実装の狙いは、バトルやダンジョンの学習段階と装備・アーキタイプの成長段階を適切に噛み合わせ、進行の停滞を避けることにあります。
ゲーム中はシステム設定から難易度を見直せる設計で、一部モードのみ途中変更ができない制限が設けられています。
難易度は大きく、与ダメージ・被ダメージの倍率、敵の行動機会や行動パターン、バトルのリソース圧(回復やバフ・デバフ、累積リスク)のかかり方に影響します。
これらの変化は、同じ敵編成でも求められる戦術判断を変え、装備やスキル構築の再考を促します。
難易度の段階は5つが案内されており、ゲーム中の変更に対応するモードと、選択後は固定されるモードが混在します。
最下位寄りの物語重視系モードと、クリア後に解放される最上位モードは固定仕様であるため、到達前に自分の目的(物語重視か、熟練プレイか、トロフィー狙いか)を決めておくと後悔を避けられます。
難易度は初期設定で最適解を選ぶよりも、区間ごとに最適化を繰り返す運用の方が実利的です。
詰まりを感じたら一時的に下げ、学習が進んだら戻す、あるいは上げて検証するという流れが、プレイ時間と達成度の両面で効率を高めます(出典:アトラス公式ニュース「試遊 大阪・東京体験会の感想」)。
あわせて、ゲームは定期的に修正アップデートが提供されています。
とくに周回データの生成不具合修正や挙動調整など、難易度の体感に関わる修正が含まれる場合があるため、最新バージョンへの更新を前提に判断するのが堅実です。
難易度における違いの明確な比較
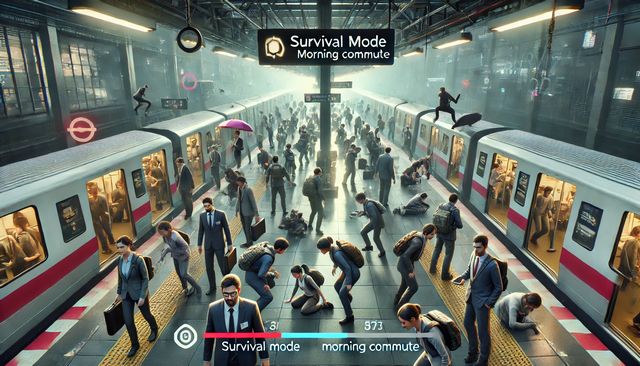
難易度ごとの性格を、プレイ判断に直結する観点で整理します。
倍率の細目は非公開ですが、難易度が上がるほど敵の行動機会の増加や被ダメージの増加など、戦術的要求が高まる傾向があります。
下表は代表的な差分と注意点のまとめです。
固定モードの存在や変更可否は進行計画に直結するため、事前の確認を推奨します。
| 難易度名 | 与ダメ傾向 | 被ダメ傾向 | 報酬傾向 | 変更可否 | 解放時期 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS ON THE STORY | 高め | 低め | 高め | 選択後は不可 | 最初から | 全滅時の即復帰が可能で物語重視向け |
| BEGINNER | やや高め | 低め | やや高め | 可 | 最初から | 基本を学びつつテンポ良く進めやすい |
| NORMAL | 標準 | 標準 | 標準 | 可 | 最初から | 初回はここからが無難な基準 |
| HARD | 低め | 高め | 標準 | 可 | 最初から | 一般敵の行動数が増える調整が入る |
| KING OF KINGS | 低め | 高め | 標準 | 選択後は不可 | クリア後 | 戦闘のやり直し制限など追加ルールあり |
表の読み方として、可変モード(BEGINNER/NORMAL/HARD)は学習や検証に使い、固定モード(FOCUS ON THE STORY/KING OF KINGS)は目的別の最終到達点として扱うと計画が立てやすくなります。
難易度による報酬傾向の差は、経験値・資金・素材の獲得速度に波及し、育成カーブの形状を変えます。
育成ルートの最適化を狙うなら、序盤は可変モードで詰まりを解消しつつ進行し、装備・スキルの土台が整った後に上位難易度へ段階的に移行するのが合理的です(出典:アトラス公式ニュース「試遊 大阪・東京体験会の感想」)。
また、収集目標の全回収や周回前提の計画を立てる際は、実装済みの実績数・トロフィー総数も把握しておくと見通しが良くなります。
PC版の実績は44個であることが公式のグローバル統計から確認できます
キングオブキングスに挑戦するポイント

最高難易度であるキングオブキングスは、失敗のコストが高く、開始後の難易度変更もできません。
挑戦の前提として、攻略資源(装備の強化段階と耐性の整備、消耗品のストック、スキル構成と役割分担、事前の弱点・行動把握)をチェックリスト化し、戦闘前の準備を形式知として固定化しておくと突破率が安定します。
最上位モードはクリア後に解放される設計で、習熟したビルドとダンジョン知識を持ったうえで挑むことが前提に近い位置づけです。
事前準備の骨子
キングオブキングスでは、個々の戦闘最適化に加え、区間全体の資源曲線を崩さない計画が成否を分けます。
編成面では、単一の弱点依存を避け、属性カバーと行動阻害を両立させたローテーションを構築します。
装備は耐性と状態異常対策を優先し、ボス戦に備えて特効・高倍率の一撃準備(バフの段積みやデバフとの噛み合わせ)を前提にします。
消耗品は上限管理と使用基準を明文化し、事故率の高い局面では惜しまず投入します。
これらの前提が揃っていてはじめて、高難度特有の被ダメージ圧や連続行動に耐えられます。
開始直後の立ち回り
序盤は装備・スキルの噛み合い不足によるダメージレースの劣勢が起こりやすい局面です。
先制獲得手段を統一し、脅威度の高い敵を順に排除して手数を減らします。
敵の強化行動や範囲攻撃の予兆に合わせ、守勢選択と単体回復を前倒しする判断が被害総量の抑制に有効です。
弱点露出タイミングで火力を集中し、行動不能・弱体系の重ねがけで被弾ターンを圧縮します。
よくある失敗と回避策
連戦区間での過剰攻撃によるMP枯渇、耐性穴の放置、ボス前の消耗品不足は典型的な敗因です。
各区間の終端で装備・耐性の差し替えをルーティン化し、次区間の主要ギミックに合わせたスキルセットへ更新します。
全滅時のロスが重いモードであるため、無理に突き進まず手戻りのラインを早めに引くことが、最終的には時間短縮につながります。
最新パッチの適用状況は挙動や安定性に関わるため、挑戦前に確認するとよいでしょう。
難易度選択時のおすすめ基準

難易度の初期選択はプレイヤーの目的とプレイスタイルに大きく左右されます。
標準的なゲーム体験を求める場合はNORMALが基準になりますが、この選択は固定ではなく、プレイ進行に応じて柔軟に変更していくことが望ましいです。
例えば、物語をスムーズに進めたい場合やアクション部分での負担を軽減したい場合はBEGINNER寄りを選び、逆に戦術検証やスキル構築の検証を楽しみたい場合はHARD寄りが適しています。
難易度は、与被ダメージのバランスや敵の行動頻度だけでなく、戦闘のテンポやリソース消費の度合いにも影響するため、難易度変更は進行計画の一部として組み込み、特定の区間ごとに見直す運用が合理的です。
また、周回前提で全要素の回収を計画する場合、1周目は難易度を柔軟に変更しつつ物語とサブ要素を広く消化し、2周目以降に高難度へ挑戦する二段構えが効率的です。
これにより、1周目の段階で難易度に起因する詰まりを回避しつつ、2周目で育成や装備を最大限活用して高難度クリアやトロフィー取得に集中できます。
トロフィー獲得を目指す場合の注意点

本作のトロフィーは合計44個で、プラチナ1個、ゴールド3個、シルバー8個、ブロンズ32個に分類されています。
全てを取得するには約120から150時間程度が必要とされ、1周での完全達成は難しい設計です。
その理由として、最高難易度に関連するトロフィーや時限要素の存在が挙げられます。
これらは特定のストーリー進行中や期間限定条件を満たす必要があるため、1周目での達成は現実的ではありません。
効率的に進めるには、1周目で取り逃しやすい時限イベントやサイドクエスト、収集物を可能な限り網羅し、2周目で高難易度や特殊条件に挑戦する流れが望ましいです。
また、トロフィー条件を事前に把握し、チャプターごとにチェックリストを作成すると、取りこぼしを防げます。
さらに、アップデートやイベント追加に伴い新たな条件が加わる可能性もあるため、公式情報の確認も欠かせません。
メタファーの難易度攻略の実践ガイド

難易度の仕組みを理解したら、次は実際にどう攻略を進めるかが鍵となります。
メタファー:リファンタジオでは、トロコンを狙うための周回計画や、難易度変更を活用した効率的な進行、事前準備の精度が結果を大きく左右します。
本セクションでは、高難易度特有の強敵「キング」への対策や、ハードモードで生き残るための立ち回り、2週目ならではの経験値活用術まで、実践的なテクニックを網羅。
さらに、難易度選択の最適な切り替えタイミングや、高い難易度を突破するための工夫も詳しく解説し、安定攻略と達成感の両立を目指します。
トロコンを達成するための手順
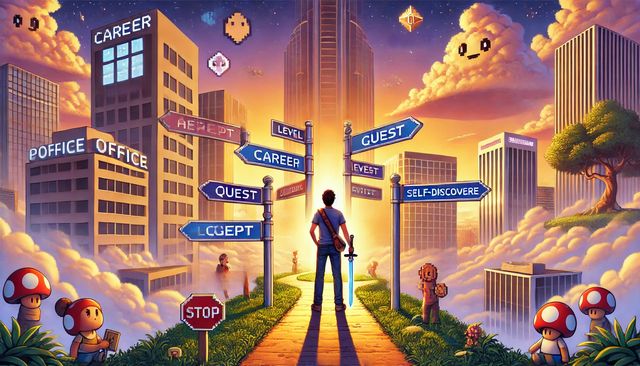
全トロフィー取得、いわゆるトロコンを達成するための基本戦略は、1周目と2周目で明確に役割を分けることです。
1周目では、メインストーリーと同時に重要なサブ条件や時限要素を回収し、可能な限り多くのトロフィーを取得します。
この際、特に期間限定イベントや進行に応じて消失する収集物の確保が優先事項となります。
2周目は、引き継ぎ要素を最大限活用して高難度や残ったトロフィー条件を攻略します。
難易度KING OF KINGS関連の条件や、高火力・高耐久の敵が登場するクエストもこの段階で集中して取り組むと効率的です。
また、2周目以降では戦力の底上げが前提となるため、戦術の幅を広げることが可能になります。
全体で100時間を超える長期計画になるため、進行状況を定期的に記録し、未達成項目を可視化することでモチベーション維持と時間短縮が図れます。
難易度変更によるメリットとデメリット

難易度を変更できる柔軟性は、プレイヤーにとって戦略的なアドバンテージとなります。
特に可変モード(BEGINNER、NORMAL、HARD)では、詰まりを感じた際に難易度を一時的に下げることで、物語進行の停滞を回避できます。
これにより戦闘に割く時間を削減し、サブクエストや収集要素の回収に充てる余裕が生まれます。
一方で、高難易度に挑戦することで得られるスキル運用の熟練度や、報酬の増加(経験値・資金・レアドロップなど)を活かしやすくなるメリットもあります。
しかし、最下位難易度(FOCUS ON THE STORY)と最上位難易度(KING OF KINGS)は選択後の変更ができません。
特に最上位モードは高い戦術理解と装備構築が必須であり、途中で撤退する場合のロスが大きいです。
そのため、これら固定モードを選ぶ際は、自身の戦力や装備状況を慎重に判断する必要があります。
可変モードの期間に十分な検証を行い、スキルの相性や装備の強弱を把握してから固定モードへ進むことが、安全かつ効率的なプレイに繋がります。
効率的な攻略のための準備
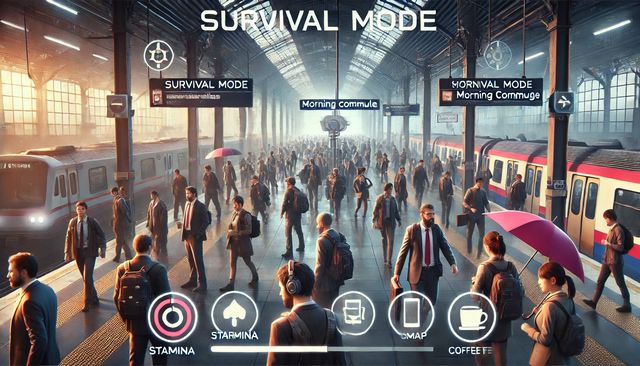
高難度になるほど事前準備の質が勝敗を大きく左右します。
まず、パーティ全員が異なる属性攻撃をカバーできるように編成することが基本です。
これにより、敵の弱点を突く機会が増え、行動の主導権を握りやすくなります。
さらに、行動順の最適化を意識したスキル配分や、状態異常・弱体化スキルの活用により、長期戦での安定性を確保できます。
装備面では、防御力や攻撃力の単純な数値強化だけでなく、特定属性の耐性や状態異常無効化といった効果を重視します。
雑魚戦では、先制攻撃を取るための素早さ調整や特定スキルのセットを事前に整えておくと被害を大幅に抑えられます。
また、消耗品は高価であっても緊急時に惜しみなく使用する基準を設定しておくことが重要です。
これらの準備を事前に固めておくことで、高難易度の長期探索や連戦にも安定して対応できるようになります。
キングを倒すための戦略

キングと呼ばれる強敵は、複数回行動や広範囲攻撃、連続ギミックによってパーティの弱点を突いてきます。
これに対処するためには、まず敵の行動パターンや耐性情報を入念に把握することが不可欠です。
予兆行動が見えたタイミングで防御系バフを重ね、被弾が集中しやすいキャラクターには単体回復やシールドを優先的に適用します。
攻撃面では、弱点が露出したタイミングに合わせて全力で火力を集中し、一気にHPを削ることが効果的です。
この際、行動不能や防御低下といった状態異常を重ねることで、敵の手数を減らしつつ被ダメージを抑えられます。
さらに、連戦や消耗戦になることを想定し、リソースの消費量を管理しながら戦うことが、安定して勝利を収める鍵となります。
キング戦はプレイヤーの準備力と判断力が試される局面であり、全滅のリスクを最小限に抑えるためには事前の綿密な戦術設計が欠かせません。
ハードモード攻略に必要な心構え

ハードモードは、敵の行動機会が増加する仕様が特徴で、短期決戦の失敗がそのまま敗北に直結する緊張感の高い難易度です。
特に雑魚戦でも油断が許されず、先制攻撃を逃すと被ダメージが一気に蓄積し、戦闘後のリソース回復に多大な負担がかかります。
このため、先制獲得のための行動順や素早さ調整、装備の選択は常に最適化しておく必要があります。
また、全体攻撃スキルは威力が高く便利ですが、消費MPが大きいため、使用基準を明確にし、複数戦闘を見据えた運用を行うことが重要です。
敵の弱点属性に対応できない場合は、あらかじめプランBとしての補助スキルやデバフ戦術を用意しておくと、攻撃が通りにくい状況でも安定して戦えます。
ダメージレースに持ち込むより、被弾抑制や行動阻害を重視することで、長期探索時の安定性を確保できます。
さらに、連戦区間ではMPや回復手段の温存が鍵となり、街へ戻るタイミングを早めに設定することで事故率を大きく減らせます。
2週目プレイで得られる経験値
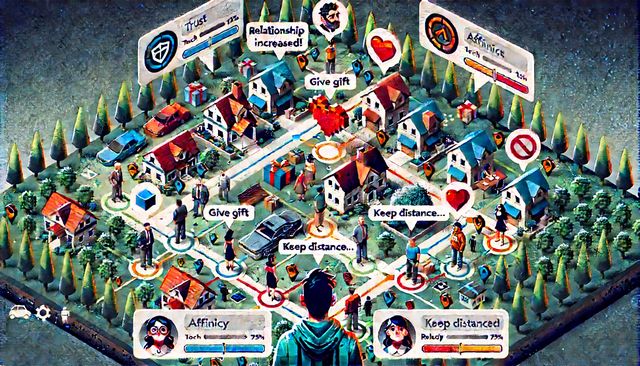
2週目は、装備・スキル・資源面が1周目より充実しているため、効率的な経験値獲得が可能です。
このアドバンテージを活かし、未消化のサブクエストや期間限定イベントを回収しながら、高難易度での戦闘を積極的にこなすことが推奨されます。
高難易度では戦闘ごとの取得経験値や報酬が増える傾向があるため、育成スピードを加速させるチャンスとなります。
また、2週目では敵の行動パターンやマップ構造を把握しているため、戦闘回数を最小限に抑えつつ必要な経験値を確保するルート設計が可能です。
序盤はレベルアップの効率が高い敵を優先的に狙い、中盤以降はボス戦や高報酬クエストに集中することで、短時間で育成のピークに到達できます。
さらに、トロフィーや実績の収集もこの段階で進めやすく、1周目での取りこぼしを補完しながら全体進行を加速させられます。
難易度選択を変えるタイミング

難易度変更は、プレイ中の詰まりや効率低下を感じた瞬間が最適なタイミングです。
たとえば、ダンジョン内での連敗やボス戦のギミックが理解できず進行が止まっている場合、一時的に難易度を下げて挙動や弱点を確認し、その後元の設定へ戻す方法が有効です。
逆に、雑魚戦が作業化して緊張感が失われていると感じたら、難易度を引き上げて刺激を取り戻すのも効果的です。
システム設定から難易度を即座に変更できる柔軟性は便利ですが、最下位難易度と最上位難易度は選択後に固定されるため、これらを選択する際は慎重な判断が必要です。
特に固定モードへの移行は、プレイヤーの戦力や目的が十分に整っている段階で行うことで、途中撤退による時間的ロスを防げます。
難易度変更を区間ごとの戦略要素として活用することは、効率的な進行とモチベーション維持の両面で効果があります。
高い難易度を乗り越えるための工夫

高難易度では、戦闘ごとに求められる判断速度と精度が格段に上がります。
特に意識すべきは、先制の獲得、弱点への集中攻撃、行動阻害、被弾管理という4つの柱です。
これらを同時に成立させるには、パーティ構成と行動計画の両面で綿密な準備が必要になります。
先制獲得のためには、素早さや行動順を調整し、敵が行動する前に脅威度の高い敵を排除する流れを確立します。
弱点集中は、全員が異なる属性攻撃手段を持つことで、どの敵に対しても迅速に弱点を突ける状況を作ります。
行動阻害については、スタン、眠り、麻痺などの状態異常やデバフを組み合わせ、敵の行動回数そのものを減らすことで、被害総量を抑えます。
被弾管理は、高火力スキルによる瞬間的な大ダメージよりも、長期戦での安定を意識した回復や防御バフのタイミングが重要です。
特に、一般敵の行動数が増える高難易度では、開幕で優先的に危険な敵から順番に撃破し、敵の手数を減らすことが事故防止に直結します。
また、場面ごとに耐性装備や支援役のスキルセットを頻繁に入れ替え、状況適応力を高めることも勝率向上の鍵です。
さらに、消耗品の使用基準を事前に明確に決めておくことで、判断の迷いによる敗北を防げます。
回復や蘇生のタイミングを早めに設定し、被害が蓄積する前に立て直す姿勢が、長期的な攻略安定化につながります。
これらの戦術を徹底することで、高難易度の壁を乗り越える確率を着実に高めることができます。
【まとめ】メタファーの難易度について
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


