シューベルト即興曲90-2の難易度について調べている方の多くは、「この曲は自分に弾けるのか?」「発表会で演奏できるレベルなのか?」といった不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。
この作品は、三連符が連続する流麗なメロディと、感情の起伏を伴う中間部が印象的な楽曲です。
一見シンプルな楽譜に見えても、実際にはテンポの維持や音の粒をそろえるなど、演奏に高い集中力と技術が求められます。
この記事では、反田恭平さんの演奏スタイルにも触れつつ、シューベルトの背景や解説を交えながら、何歳から取り組めるのか、ゆっくり練習でどのように攻略すべきか、具体的な弾き方や注意点を丁寧に紹介します。
また、同じ作品集の90-3 難易度や、技巧的に難しいとされる90-4との比較も行い、全体の位置づけを明確にしていきます。
発表会での演奏を目指す方にも役立つ内容を網羅していますので、ぜひ参考にしてください。
■本記事のポイント
- 楽譜の構造と演奏上の技術的な難しさ
- 発表会で効果的に演奏するためのポイント
- 他の即興曲(90-3・90-4)との難易度比較
- ゆっくり練習や弾き方の具体的な対策方法
シューベルト即興曲90-2難易度を徹底解剖

シューベルトの即興曲90-2は、美しくも絶え間ない三連符が特徴的な楽曲です。
一見シンプルに見える構成ですが、実際に演奏してみると、思いのほか手強いと感じる方も多いでしょう。
楽譜上の難易度だけでは見えてこない本当の難しさや、練習を重ねる中で直面する技術的な壁など、演奏者のレベルに応じて課題が変化していきます。
ここでは、楽譜の構造や演奏技術の観点から、この曲の本質的な難易度に迫り、攻略のヒントを深掘りしていきます。
楽譜から見た難易度のポイント
まず、楽譜を見れば「シューベルト 即興曲 90-2」はHenle版や全音ピアノピースなどで難易度“D”または“6”(中級)とされていることがわかります。
ただし、数字以上に難しく感じるポイントも存在します。
というのも、右手では絶え間なく続く三連符のスケールや跳躍が中心となっているため、スムーズかつ均質な演奏が求められるからです。
例えば、譜面を見ると主部で上下に駆け回る三連符が延々と書かれており、楽譜上はシンプルに見えても実際にはタイミングや音量調整が難しく、ミスが目立ちやすい構造です。
さらに、この形式はmoto perpetuo(常動)型で中間部を含む3部形式になっているので、演奏時間は約4分半~5分と長めで、持久力や集中力も必要です。
したがって、楽譜上の難易度評価は中級でも、実際には「スケールや速度が途切れずに続き、集中力も必要」という理由から、演奏を想定した練習では注意すべき点が多いと言えるでしょう。
解説 背景を交えた難しさの理由
現在の演奏・研究情報によると、この作品はシューベルト晩年の1827年に作曲され、その中でも特に技巧と感情表現のバランスが問われる作品として知られています。
背景として、当時の即興的な短篇作品の中でも、この曲は自由度と構成性を併せ持つ技巧的エチュード的要素が強く表れており、「moto perpetuo」に対してドラマティックな中間部を挟む3部形式で構成されています。
一方、単なる技巧練習曲ではなく、バッハやベートーヴェンにも通じる起承転結の構造美があり、聴き手に訴える情感をどう表現するかが問われます。
シューベルトのほかの即興曲(Op.90-3、4)と比較すると、90-2では「華やかで速いパッセージ+情熱的中間部+熱いコーダ」という、表現の幅が特に大きく、ただ速く弾くだけではなく対比の演出が必要です。
また、Youtubeやピアノ指導記事では、脱力を重視した演奏やスロー練習によるニュアンスづけが推奨されており、技術だけでなく音楽的表現力の深め方にも時間をかける必要があることがわかります。
このため、背景理解と技術練習を組み合わせることが、作品の深い理解と完成に繋がるでしょう。
ゆっくり練習による攻略法
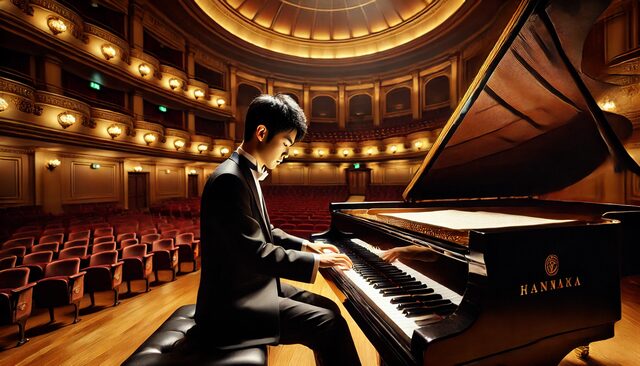
まずは、メトロノームを使って意識的に「ゆっくり」で練習することが鍵です。
ただ速く弾くのではなく、ゆったりめのテンポで三連符やフレーズを丁寧に確認しながら進めます。
そうすることで、指づかいや強弱のバランス、リズムの正確さが格段に向上します。
Arioso7氏の指導によれば、「遅く弾けないものは速くも弾けない」ため、まずは低速で確実に音を出す練習を徹底することが有効とされています。
例えば、E♭メジャーのスケールやその並行調であるE♭マイナーをゆっくり弾き、手と耳をその音色に慣れさせることで、曲全体の流れがつかみやすくなります。
さらに細かく分割して左手だけ、右手だけ、和音やオクターブをブロックで練習することで、短時間でも効率よく技術を安定させられます。
ただし注意点もあります。
ゆっくり練習に慣れすぎて、本番のテンポで弾くとぎこちなくなるケースがあるため、練習テンポは段階的に上げ、本番のリズム感もしっかり養うことが重要です。
弾き方のコツと注意ポイント
この作品では、右手に長い三連符が延々と続きます。
だからこそ脱力が最重要で、手首や腕の重みを使い、指先だけに頼らないようにします。
マキノピアノ教室では「弱い指でも粒のそろった音を出すために、アーチ構造を保つこと」が推奨されています。
また、手首の柔軟な動きが不可欠です。
時折、手首を回転させるように使いながら演奏すると、負担が分散され、筋肉疲労や音色の安定にもつながります。
左手でも低音部分をメロディのように歌わせるために、手首の角度調整が効果的です。
さらに、指くぐりのあとの弱い4番指や強い1番指の音が不安定になりやすいので、粒をそろえるための反復練習が必要です。
途中で「音が飛び出る」「急に弱くなる」などのムラは、録音して自分でチェックし、修正する習慣をつけましょう。
発表会で弾く際のおすすめポイント

発表会を意識する場合、まず「情感の対比」を明確に演出することが大切です。
冒頭の明るい三連符のパッセージと、中間部のBマイナー部分のドラマティックな旋律をメリハリよく演奏することで、聴き手に強く印象を残せます。
さらに、テンポ設定にも工夫が必要です。
速すぎると雑に聞こえ、遅すぎると流れが止まるため、自分が安定して演奏できる限界速度を見極め、それを少し余裕を持って遅めに設定するのがポイントです。
一方で、発表会ならではの緊張には注意が必要です。
事前に本番を想定した通し練習を行い、緊張対策にも取り組みましょう。
環境音や客席をシミュレーションした練習や、録画して自己フィードバックする方法も有効です。
これにより精神面の安定が図れ、演奏の完成度が上がります。
シューベルト即興曲90-2難易度と関連作品比較

シューベルトの即興曲Op.90-2を深く理解するには、同じ作品集に含まれる他の曲と比較する視点が欠かせません。
Op.90全4曲はいずれも個性的で、それぞれ異なる技術や音楽性が求められます。
特に、90-2と90-3、90-4は難易度や演奏スタイルの違いが顕著で、学習者にとって「どれが自分に適しているのか」「どんな準備が必要か」を考えるヒントになります。
ここでは、それぞれの特徴を整理しながら、効果的な選曲や練習の参考になる情報をお伝えします。
90-3難易度との比較

90-2と比べて、90-3(G♭メジャー)はテンポが遅く、旋律も穏やかなため「中級」の難易度に感じられることが多いです。
楽譜上ではHenle版でも「6・medium」に分類され、技術的には90-2と大差ないとされていますが、実際には演奏スタイルが大きく異なります。
というのも、90-3は三連符によるmurmuringな左手伴奏と、右手の静かな旋律が続く構造で、速度よりも表現の一貫性とペダリングが問われるからです。
例えば、Henleの記述でも「静かで夢のような瞑想的作品」とあり、細やかな音色のコントロールや長いフレーズを持続する集中力が求められるとされています。
Redditのピアニストからも、「長くても簡単すぎてエグザムに選ばれないレベル」と評される一方で、音楽的な深みを要求される内容だと見なされています。
したがって、テクニカルには90-2と近いものの、90-3は精神面の精緻さや表現の細部に配慮が必要で、初心者にとってはむしろこちらの方が心理的な難関となり得ます。
90-4との難易度比較

一方で、90-4(A♭メジャー)は高速なアルペジオやスケール、両手によるオクターブ下降など、非常に技巧的な要素が詰まった作品で、4曲中もっとも難易度が高いとされています。
PianoStreetやPianoWorldフォーラムでは「技術的にこれが一番手ごわい」という声も多く、Henleではやはり“6・medium”に分類されながらも、ピアニストからはGrade7から8相当と評価されることもあります。
この作品は技巧だけでなく、全体を通じて一定の勢いを保ちつつ、強弱やアクセントの変化をつけていく表現力も問われます。
具体的には、右手のアルペジオを滑らかにしながら、左手で対位的なフレーズを響かせる必要があります。
また後半ではリズムの跳躍やトリルが重なり、瞬間的な反応力と集中力が求められます。
したがって、技術面・集中力・表現力のすべてを高水準で備えていないと難しい作品であり、90-2とは明らかにレベルが異なる「上級」に相当すると言えるでしょう。
全音ピアノピース難易度一覧との位置関係

全音ピアノピースは、AからFまでの6段階で楽曲の難易度を示しています(A=初級からF=上級上)。
即興曲Op.90-2は「D」(中級上)に分類されており、シリーズ全体では中から上級域に位置します。
これは他の中級上クラスの作品、例えばシューベルトやショパンの小品と同等の技術が要求されるレベルです。
一方で、同じDクラスには「華麗なる大円舞曲」や「悲愴ソナタ」などの比較的大きな規模や技巧を必要とする曲も含まれており、Op.90-2の楽譜量や技術的負荷を考えると、自身の感覚では「これらよりもやや易しい」と感じる方もいるかもしれません。
そのため、全音の難易度一覧はあくまで目安であり、作品ごとの特色や演奏者の得意不得意によって体感は異なることを理解する必要があります。
全音ピアノピース難易度Dは妥当か?

「難易度D=中級上」という評価は、楽譜の分量・テクニックの種類・表現の幅などを総合的に判断した結果です。
ツェルニー30~40番程度の技術を習得していれば対応可能とされていますが、Op.90-2は三連符の連続、持続するフレーズ、テンポの維持など技術的・精神的負荷が重なるため、評価としては納得できると言えます。
ただし、「おかしい」と感じる声も多く、特に古典派作品の軽快さや表現を重視したものに比べてD以上に感じる楽曲も多数あります。
体感として「難易度Dは妥当だけれど、内容の濃さ・持久力から見ると妥当以上の挑戦」と思う人も少なくありません。
そのため、難易度はあくまでガイドラインと捉え、自分の技術や演奏目的に照らして判断することが大切です。
何歳から取り組める?

この作品は一般的には中学生~大人の中級者が挑戦する曲として知られており、ピアノ歴3~4年程度が目安です。
実際にYahoo!知恵袋では「中級、大人の人でも3~4年熱心に練習していれば弾けるようになる」との声があります。
さらに、小学校高学年以上でチェルニー30番以降を学んでいると、自信を持って楽譜に取り組めるようになります。
もちろん個人差は大きく、練習頻度やレッスン環境により、8~9年の経験があれば小学生でも演奏できる場合もあります。
ただし難しいのは中間部の転調や、テンポ維持しながら三連符を正確に演奏する点です。
だからこそ、技術的な基盤をしっかり築いたうえで挑むことが成功の鍵になります。
もっと言えば、「この曲をやってみよう」と思えたタイミングで意欲を持って練習を始められることが大切です。
反田恭平さんの演奏スタイルを参考に
反田恭平さんの演奏には、研ぎ澄まされた表現力と抑制されたテンポ感が光ります。
特にゆっくりした部分やp(ピアノ)のニュアンスが美しく、声をかけるような語り口を持つ演奏が多くのリスナーに支持されています。
この作品の攻略に当たっては、反田さんのように急がず歌うように演奏するスタイルが参考になります。
ただし、技術が伴わなければゆったり演奏は形だけになりがちです。
そのため、安定したテンポ感と脱力の練習を並行させながら、感情を込めて歌わせる演奏を目指すと良いでしょう。
反田さんに倣って、音色の変化や旋律線の歌い方にこだわることで、技術以上に聴き手の心に響く演奏を目指せます。
【まとめ】シューベルト即興曲90-2難易度について
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


