maimaiをプレイしていると、maimaiの難易度という言葉の意味や仕組みを詳しく知りたくなる場面が増えてきます。
本記事では、難易度表の見方をはじめ、プレートや将プレート、神プレートの取得条件についてもわかりやすく解説していきます。
また、カレイドスコープなど特別な称号との関係、段位認定における難易度の目安、そして理論値を取るために必要なスキルについても紹介します。
さらに、適正難易度の見極め方や12、14、15といったレベル帯ごとの特徴、ランキング上位に入る曲の傾向も取り上げます。
記事内では楽曲の名前と難易度との関連性、難易度改定における注意点、プレートごとの色が示す実力の違いも整理しました。
最後に、maimaiの難易度を難易度順にする方法や、練習手順についても詳しく触れていますので、一覧形式で確認しながら、自分に合った攻略法を見つけていきましょう。
■本記事のポイント
- maimaiの難易度とプレート獲得の仕組みを理解できる
- 難易度別の特徴や段位ごとの目安を把握できる
- 難易度表を活用した練習方法と上達手順がわかる
- 難易度改定やランキング上位曲の傾向を知ることができる
maimaiの難易度とは?仕組みをわかりやすく解説

maimaiには難易度という明確な指標が存在しますが、その仕組みを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。
難易度は単なる目安ではなく、プレイヤーの実力や成長段階を知るうえでとても重要な役割を果たしています。
ここでは、maimaiにおける難易度の基本的な考え方を解説しながら、プレイスタイルや目標設定にも役立つ知識をわかりやすく紹介していきます。
これから詳しく見ていく「適正の考え方」や「各レベル帯の特徴」についても、ぜひ参考にしてください。
maimaiの難易度とプレートの関係
maimaiの難易度とプレートには、密接な関係があります。
プレートとは、ゲーム内で一定の条件を満たしたときに獲得できる称号のようなもので、プレイヤーの実力や達成度を示す役割を持っています。
多くのプレイヤーにとって、プレートは一種の目標設定であり、やり込み要素でもあるのです。
まず、maimaiの譜面難易度は「12」「14」「15」といった数値で表されており、この数字が高いほど譜面のクリアや高スコア取得が難しくなります。
そして、獲得できるプレートの種類も、この難易度に応じて変わってきます。
例えば、難易度12の譜面を一定数以上クリアすれば取得できるプレートもあれば、難易度14や15の譜面で高スコアを出さなければならないプレートも存在します。
これには、プレイヤーの地力向上を促す意図もあります。
難しい譜面に挑戦することで自然と技術が身に付き、同時に上位プレートの獲得にも近づくためです。
一方で、プレートを狙う際には注意点もあります。
それは、難易度ばかりを意識してしまい、本来の楽しみ方を見失いやすいことです。
プレート獲得に焦るあまり、譜面を楽しめず、結果的にモチベーションを落としてしまうケースも少なくありません。
このように考えると、maimaiにおける難易度とプレートの関係は、単なる技術力の証明だけでなく、プレイヤー自身の成長過程やゲームの楽しみ方にも大きく関わっていると言えます。
自分のペースで無理なく、楽しみながら挑戦していくことが、結果的には効率良くプレート獲得につながるでしょう。
将プレートとは何か?基準を解説
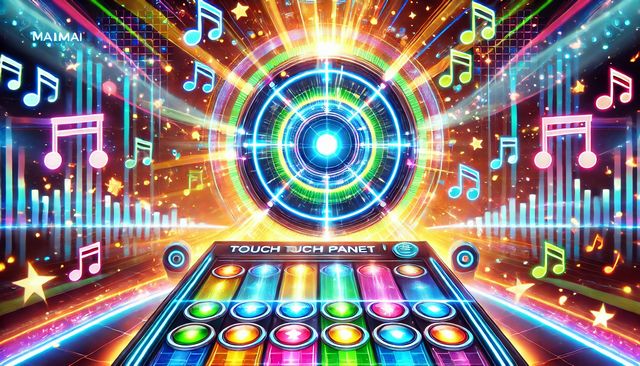
将プレートとは、maimaiにおける一定の実力達成を示す特別なプレートの一つです。
ゲームに慣れたプレイヤーであれば一度は目にする機会があり、その取得は一つの大きなステータスとも言えます。
将プレートの基準は、ある程度高めに設定されています。
具体的には、難易度14以上の楽曲において高いスコア、たとえばフルコンボや鳥プラ(100%以上のスコア)を複数達成することが求められます。
対象楽曲数や必要な達成スコアについてはバージョンごとに微調整されることもあり、特に新しい楽曲が追加された直後は取得難度が変わることもあります。
ここで注意すべきなのは、将プレートは単純なクリアだけでは取得できないという点です。
通常クリアではなく、正確なタップ、スライド操作、イーチノーツへの対応など、譜面全体を高い精度で攻略する必要があるため、ある程度の総合力が求められます。
これを知らずに挑戦すると、なかなか条件を満たせず挫折してしまうかもしれません。
一方で、将プレートを目標にすることで練習内容に方向性が生まれるメリットもあります。
漫然とプレイするのではなく、「この譜面のこのセクションを安定させよう」と意識できるため、結果的に地力全体の底上げにつながることも多いです。
このように、将プレートはmaimaiを本格的にやり込むプレイヤーにとって大きな指標となりますが、取得には確かな準備と練習が必要です。
焦らず自分の成長を楽しみながら目指していくことが、取得への一番の近道となるでしょう。
神プレート取得に必要な難易度

神プレートは、maimaiにおける最高峰のプレートの一つであり、取得するには相当な実力が求められます。
このプレートを手に入れるためには、単純にたくさんプレイするだけでは足りず、特定の高難易度譜面に対して安定して高スコアを出す能力が必要です。
まず大前提として、対象となる譜面の難易度は「14」や「15」といった極めて高いレベルのものが中心です。
12や13といった難易度では、いくらスコアを出しても神プレートの条件を満たすことはできません。
また、ただクリアするだけでは条件に届かず、鳥プラ(スコア100%以上)を安定して取得できることが求められます。
これは、正確なリズム感や譜面認識力、持久力、そして微細なタップ精度までが問われるレベルです。
ここで意識しておきたいポイントは、特定の譜面だけをやり込むだけでは足りないということです。
神プレートの取得条件には、様々なタイプの譜面に対応できる汎用的なスキルも含まれています。
例えば、速いBPMへの対応、変則リズム譜面の攻略、複雑なスライド操作など、まさに総合力が必要となるのです。
しかし、これだけ高いハードルであるがゆえに、途中で挫折してしまうプレイヤーも少なくありません。
スコアが思うように伸びない場合には、無理に詰め続けるよりも、一度譜面研究や運指改善に立ち返ると、結果的にスムーズに成長できるケースも多いです。
このように考えると、神プレート取得に必要な難易度は「14以上」であり、かつ単なるクリアを超えた超高精度プレイが求められると理解しておく必要があります。
目指す価値は非常に高いですが、無理をせず、自分のペースでステップアップしていくことが大切です。
カレイドスコープと難易度の関係

カレイドスコープとは、maimaiにおけるプレートやスコアランキングとはまた異なる特別な称号や報酬の一種で、主に一定期間のイベントや特定のチャレンジを達成したプレイヤーに与えられるものです。
その取得条件と難易度には、密接な関係があります。
カレイドスコープを得るためには、指定された課題曲で高得点を取る必要がある場合が多く、通常の楽曲選択とは違ったプレイスタイルを要求されることもあります。
課題曲には14~15の高難易度譜面が設定されるケースが非常に多く、結果として自然と難易度の高いプレイを求められることになります。
これにより、単なる地力だけでなく、短期間で特定譜面を攻略する能力も試されるのです。
また、カレイドスコープを目指す際には、1曲だけでなく複数曲をバランスよく高スコアでクリアする必要があるパターンが見られます。
そのため、得意な譜面だけでなく、苦手な譜面にも向き合う必要があり、結果的にプレイヤーの総合的な実力向上にもつながります。
一方で、短期間で要求される条件を満たさなければならないため、時間的なプレッシャーも大きいのがデメリットです。
忙しい時期に重なると、取得を断念せざるを得ないこともあり得ます。
この点については、事前にイベントスケジュールを確認し、自分のプレイ計画を立てることが重要です。
このように、カレイドスコープと難易度の関係は非常に密接であり、単なる運ではなく高い実力と計画性が求められるものです。
高難易度への挑戦は厳しいものですが、その達成感は非常に大きいため、maimaiをさらに深く楽しむための大きなモチベーションにもなるでしょう。
難易度と段位の目安

maimaiにおける段位認定は、プレイヤーの実力を示す大切な指標のひとつです。
そして段位と難易度の関係は、プレイヤーが目標を設定するうえでも非常に重要な要素となっています。
ここでは、段位ごとのおおよその難易度目安について解説します。
まず基本的に、初級段位である「初段」「二段」などは難易度12~13程度の楽曲が対象になることが多く、音ゲーに慣れ始めたプレイヤーがクリアを目指しやすい構成になっています。
一方で、中級段位である「四段」「五段」と進んでいくと、求められる難易度も自然と上がり、13+や14の譜面を安定して攻略できる力が必要となってきます。
そして上級段位である「七段」「皆伝」などでは、14以上の高難易度楽曲が頻繁に出題されるようになります。
特に皆伝では、15レベルの譜面を高スコアでクリアすることが要求される場合もあり、単純な譜面クリアだけでなく、精度の高さやスタミナ、譜面研究力までが問われます。
段位認定を目指す上で意識したいのは、ただ高難易度曲に挑戦するだけでは不十分だということです。
段位課題曲は体力、リズム感、譜面認識などあらゆる能力をバランスよく求められるため、得意ジャンルに偏らず総合的な地力を伸ばすことが重要です。
このように、maimaiの難易度と段位の目安は密接に関わっており、段位ごとにおおよその難易度帯が定まっています。
段位認定に挑戦する際は、事前に課題曲の難易度を把握し、計画的に実力を積み重ねていきましょう。
理論値を取る難しさとポイント

maimaiにおいて「理論値」とは、1曲で一切のミスもグレート判定も出さず、全ノーツをパーフェクトで叩き切った状態を指します。
この理論値を取ることは、ゲーム内でも最高レベルの達成であり、非常に難しい目標となります。
まず、理論値を狙う難しさの一つは、単なる譜面クリアとは比較にならない精密なタイミング要求にあります。
1回でもわずかにタップが早かったり遅かったりすると、すぐにグレート判定となって理論値は崩れてしまいます。
そのため、BPMやリズムの癖を完全に身体に覚え込ませる必要があり、譜面ごとに異なる細かなリズム変化にも対応しなければなりません。
加えて、体力や集中力も大きな壁になります。
特に長い譜面や速いBPMの曲では、途中で手元がブレたり、疲れからリズムが乱れたりするリスクも増えるため、フィジカル面でも高い要求が課せられます。
ここで、理論値を取るためのポイントをいくつか挙げます。
まず、何よりも大切なのは「譜面研究」です。
タップ位置やスライドの巻き込みポイントを把握し、どの手でどのノーツを取るかをあらかじめ決めておくと、無駄なミスを減らすことができます。
次に、プレイ環境を整えることも重要です。
画面の反応や滑り具合、音の聞こえ方など、自分が最も快適にプレイできる環境を作るだけでも成功率が大きく変わります。
一方で、理論値にこだわりすぎると、かえってプレイ自体が苦しくなってしまうリスクもあります。
精神的な負担が増えると集中力が切れやすくなるため、ある程度リラックスしてプレイすることも大切です。
このように、理論値を取るためには技術、体力、集中力、譜面理解、そして適切な環境作りが不可欠となります。
簡単な目標ではありませんが、達成した時の達成感は非常に大きいため、焦らず一歩ずつ確実に取り組んでいきましょう。
難易度における適正の考え方

maimaiをプレイしていると、自分にとって「適正」と呼べる難易度を把握することが非常に大切です。
適正を知ることで、無理な挑戦による挫折を防ぎ、効率的な上達に繋げることができるからです。
まず、適正とは「現在の実力に見合った難易度帯」を指します。
例えば、14レベルの楽曲で安定してフルコンボできる、あるいは高いスコアを出せるのであれば、そのプレイヤーの適正は14だと考えることができます。
一方で、クリアすら安定しないのであれば、そのレベル帯はまだ適正とは言えません。
ここで注意したいのは、適正は単なるクリアの可否だけで決まるわけではないということです。
単にクリアできたとしても、スコアが大きくブレたり、ミスを連発している場合は、まだ適正とは言い難い段階にあります。
ある程度の安定感と再現性があって初めて、その難易度を「適正」と呼ぶべきです。
また、適正の見極めには感情に流されないことも重要です。
例えば、「好きな曲だから」といって無理に高難易度を挑戦し続けても、効果的な練習にはなりません。
適正を正しく認識し、適正より少し上の難易度に挑戦しながら、基礎力を鍛えていくのが成長への近道です。
さらに、適正は日々変動するものです。
練習を重ねることで自然と適正難易度も上がっていきますので、定期的に自分の実力を見直すことが大切です。
このように、maimai難易度における適正を正しく把握することは、スムーズな上達のために不可欠な考え方となります。
12 14 15レベル帯の特徴まとめ

maimaiにおける難易度12、14、15の各レベル帯には、はっきりとした特徴の違いが存在します。
これを理解しておくと、プレイヤー自身の目標設定や練習方針を立てやすくなります。
まず、12レベル帯についてですが、ここは基礎練習に最適な楽曲が多く揃っています。
複雑な混合フレーズや速いスライドはあまり登場せず、タップ・ホールド・スライドの基本操作を安定してこなす力が求められます。
譜面を見て正確にリズムを取れること、シンプルなパターンに対応できることが主な目標となるでしょう。
一方で14レベル帯に進むと、途端に要求されるスキルが高まります。
タップとスライドの複合操作や、画面全体を広く使った認識力が試される譜面が多くなり、単純な操作だけでは太刀打ちできなくなります。
また、体力面でも要求が大きくなるため、長時間安定してパフォーマンスを維持する力も求められます。
14レベル帯は、いわば中級者から上級者への登竜門といえるでしょう。
さらに、15レベル帯になると、プレイの質が大きく問われるようになります。
譜面の物量が急増し、乱打や高速スライド、リズム難などあらゆる要素が高度に組み合わされています。
正しいリズム感覚だけでなく、即時の判断力や反射神経、持久力に至るまで総合的な能力が試されます。
このレベル帯では「ミスをしない」だけでは通用せず、「いかに精度良く押し切れるか」という課題に直面することになります。
このように、12、14、15レベル帯それぞれに求められるスキルや特徴は大きく異なります。
これらを理解した上で、自分にとって今必要な課題に合わせた選曲や練習を行うことが、効率的な上達につながります。
maimaiの難易度表の見方と攻略法まとめ
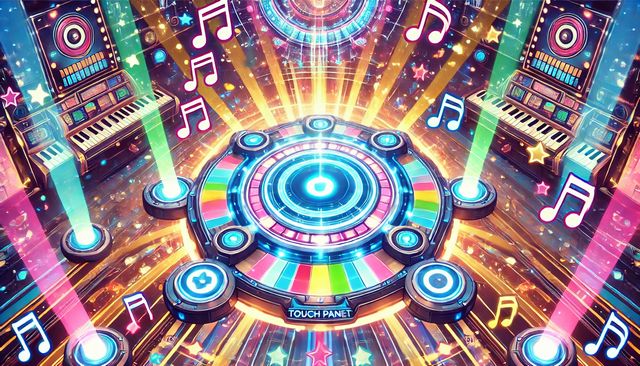
maimaiの上達を目指すなら、難易度表を正しく理解して活用することが非常に重要です。
ただ曲を選んで遊ぶだけでは、どうしても成長に時間がかかってしまうことがあります。
ここでは、maimai難易度表の基本的な見方から、練習に役立つ具体的な攻略法までをわかりやすく解説します。
プレートの色ごとの水準や、難易度順で練習するコツも紹介しますので、自分に合ったレベルアップの道筋がきっと見つかるでしょう。
それでは、順番に見ていきましょう。
ランキング上位曲の特徴を解説

maimaiにおけるランキング上位曲は、単純に「難しい」だけではありません。
多くのプレイヤーが苦戦する理由は、譜面の傾向や技術要求の幅広さにあります。
まず、ランキング上位に登場する楽曲には、リズム難・認識難・体力譜面といった要素がバランス良く盛り込まれていることが多いです。
つまり、特定の技術だけに偏らず、総合力が試される内容になっています。
さらに、これらの曲はブレイク地帯や終盤に特に難しい配置があり、一度のミスが大きな失点につながりやすい傾向があります。
そのため、単純な練習量だけでなく、譜面の研究や細かい修正力も求められます。
例えば、流し配置を耐えたあとに突発的なトリルが来るパターンなど、気を抜く隙間を与えない構成が目立ちます。
これにより、安定したパフォーマンスを保つのが非常に難しくなるのです。
このように、ランキング上位に位置づけられる楽曲は、あらゆる面で高いスキルを要求することが特徴です。
難易度曲一覧をチェックしよう

maimaiでは、すべての楽曲が一定の難易度に応じて分類されています。
この難易度曲一覧を確認することで、自分の現在地を把握したり、次に挑戦すべき曲を選んだりするのがとてもスムーズになります。
特に、レベル12、14、15など区切りとなる難易度帯では、曲ごとに要求される技術や癖が大きく異なるため、事前のチェックが重要です。
この一覧は、公式サイトや有志による難易度表などから簡単に確認できるため、計画的な練習には欠かせません。
また、曲ごとの特徴やプレイヤーからの評価も参考にできるため、単なる数字以上の意味を持つ情報源となっています。
一方で、難易度表記だけに頼ると、自分に合わないタイプの譜面に苦戦する場合もあるため注意が必要です。
例えば、物量耐久に強い人でもリズム難に弱いと、見た目よりもスコアが伸びないことがあります。
このため、一覧をチェックするときは「自分の得意不得意」も意識しながら選曲することが大切です。
曲の名前と難易度の関連性について

maimaiでは、曲の名前と難易度の間に直接的な関連は存在しません。
つまり、タイトルを見ただけで難易度を予測するのは難しいのが現状です。
しかし、実際にはある程度の傾向を把握することが可能です。
例えば、リミックスバージョンや「Re」などの表記が付いている曲は、原曲よりも難易度が高いことが多いです。
また、「EX」「ST」「MAS」などのバージョン名や譜面区分がついている楽曲は、通常バージョンと比べて配置が複雑であったり、スライドやタップの要求精度が高かったりする場合が目立ちます。
こういった副題や表記を見るだけでも、ある程度その譜面が通常より高い難易度であることを察知できるでしょう。
ただし、名前がシンプルでも非常に難しい楽曲は存在するため、タイトルだけで判断するのはリスクが伴います。
確実に難易度を把握するためには、実際に一覧表を確認するか、譜面鑑賞などで内容を把握することが推奨されます。
難易度改定時に注目すべきポイント

maimaiでは、バージョン更新やアップデートごとに難易度の見直し、いわゆる「難易度改定」が行われることがあります。
この改定において注目すべきポイントは大きく三つあります。
まず一つ目は、定数変更があった楽曲の把握です。
難易度の数値が微調整されることで、レートの伸びやプレート取得条件が変わる場合があります。
次に重要なのは、新たに14、15レベルに昇格・降格した楽曲の確認です。
特に13+から14へ昇格した曲は、急に難しく感じることが多く、今までの感覚で挑戦すると苦戦する恐れがあります。
適正レベルを意識したうえで、プレイ計画を立て直す必要があるでしょう。
最後に見逃してはいけないのは、個人差が強く影響する譜面の評価変動です。
改定では公式が基準を設けますが、プレイヤー間では「この曲はもっと難しい」「意外と簡単」と意見が分かれる場合もあります。
そのため、公式発表だけでなく、自身の体感や各プレイヤーの声も参考にすると良いでしょう。
プレートごとの色と難易度水準

maimaiでは、達成度に応じてプレートの色が変わり、その色によってプレイヤーの実力が一目でわかるようになっています。
色ごとに難易度水準が設定されており、どの色を目指すかによって必要な技術や努力量も変わってきます。
例えば、青プレートは基礎ができている段階で取得可能ですが、紫以上になると精度や対応力の高さが求められます。
さらに、赤プレート以上では単にクリアするだけでなく、高精度で譜面をこなす必要があるため、難易度14や15の曲でも一定以上のスコアを維持することが前提となります。
金色や虹色プレートになると、理論値に近いスコアや、高難易度曲の安定クリアが求められるため、プレイヤーの中でも限られた層だけが到達できるレベルとなります。
このように、プレートの色は単なる見た目以上に、プレイヤーの実力を示す重要な指標です。
自分の今の色から次の段階に進むには何が足りないのか、明確に意識しながらプレイすることが上達への近道となるでしょう。
難易度表を活用するメリット

maimaiを効率よく上達させたいなら、難易度表を活用することが非常に有効です。
難易度表を使う最大のメリットは、自分の適正に合った譜面を選びやすくなることです。
単純にプレイする曲を選ぶだけでなく、現在の実力より少し上の難易度に挑戦することで、無理なくスキルアップを目指すことができます。
また、難易度表を見ることで、似たような難易度帯の曲同士を比較しやすくなります。
例えば、14.2の曲でも押しやすい譜面と癖の強い譜面があるため、単なる数字だけでは測れない特徴を理解する手助けになるでしょう。
さらに、イベントや段位挑戦の際にも難易度表が役立ちます。
事前にどの譜面が難しいポイントを持っているか把握しておけば、戦略的に練習を進めることができます。
無闇にプレイするよりも、確実に成果が出やすくなるため、特に時間を有効に使いたいプレイヤーにとって難易度表の活用は必須と言えます。
難易度順にする方法と練習手順
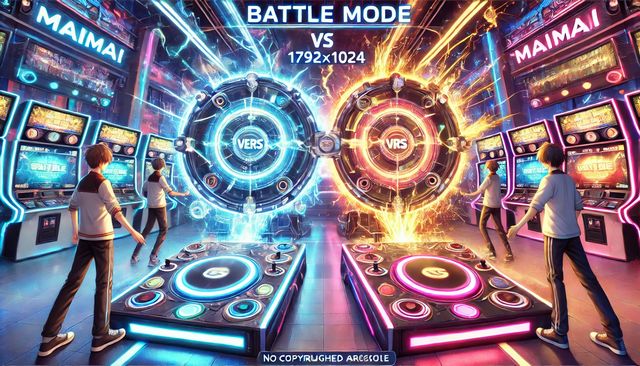
maimaiでスムーズに実力を伸ばしたいなら、譜面を難易度順に進める方法を意識するのが効果的です。
最初にするべきことは、自分の現状に合った難易度帯を見極めることです。
例えば12~13+帯が安定しているなら、次は14に挑戦する、というように少しずつ上のレベルを目指していきます。
このとき、難易度表を参照し、比較的簡単と言われている譜面から挑戦するのがポイントです。
14の中でも難易度に幅があるため、最初は14.0や14.1の譜面を中心に練習すると挫折しにくくなります。
徐々に14.3以上にステップアップすることで、自然と地力が上がるでしょう。
練習手順としては、まず譜面を通してプレイし、特に苦手な部分をメモしておきます。
その後、そのパターンを意識的に練習し、できる限り正確な運指やリズム感を身につけます。
何度もプレイするだけでなく、苦手部分のパターンを分析することが、効率的な上達には欠かせません。
このように難易度順に段階的に進める方法を取ることで、自然とスムーズなレベルアップを図ることが可能になります。
焦らず一歩ずつ進んでいきましょう。
【まとめ】maimaiの難易度について
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


