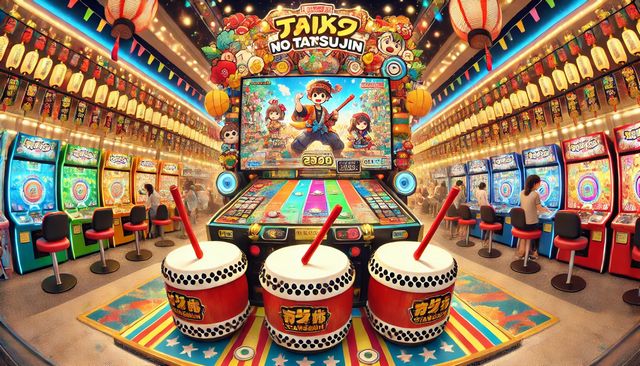太鼓の達人で全良を目指しているプレイヤーにとって、「どの譜面から挑戦すべきか」「どのくらいの難易度なのか」といった疑問はつきものです。
本記事では、太鼓の達人 全良難易度に関する情報を、最新のランキングやa、ssといった難易度ランクを交えながら詳しく解説していきます。
特に非公式の太鼓の達人 全良難易度表を活用することで、自分に合った譜面選びや全良難易度表 塗り方の工夫が可能になります。
また、ふよしやpgxなどのプレイヤー用語、難易度表 星7 星8 星9 星10の違い、さらには太鼓の達人の難易度の種類は?といった基本的な疑問にも答えながら、全良を目指す上で避けて通れない「太鼓の達人の裏鬼とは?」という要素にも触れていきます。
全良達成に向けた第一歩として、ぜひ参考にしてください。
■本記事のポイント
- 全良難易度の定義と求められるスキル
- 全良難易度表やランキングの見方と活用法
- 難易度ごとの譜面傾向や裏鬼の特徴
- 全良を目指すための練習方法と譜面選び
太鼓の達人で全良の難易度を徹底解説

太鼓の達人を本気で極めたいと考えるプレイヤーにとって、「全良」はひとつの到達点です。
しかし、同じ☆10譜面でも全良難易度には大きな差があり、何から挑戦すればよいのか迷う人も多いでしょう。
この記事では、全良難易度の特徴や最新情報、ランキングの傾向などを網羅的に解説します。
初心者から中級者、そして上級者まで、全良を目指すすべての人が次に進むべきヒントを得られるはずです。
まずは全良難易度の基本から確認していきましょう。
全良難易度の特徴とは?
太鼓の達人における全良難易度は、単にフルコンボ(コンボを切らさずに最後まで叩き切る)とは異なり、「すべての音符を可や不可なしで叩く」ことを意味しています。
つまり、1曲を通じて一度も可を出さず、すべて良(パーフェクト)で演奏する必要があります。
この難易度の特徴として、譜面の構成が非常に精密で、単なる暗記や反射神経だけでは達成が困難な点が挙げられます。
例えば、リズムパターンの複雑さや、音符同士の間隔が微妙に変化するため、安定して全良を狙うには、譜面ごとの特性を理解し、事前に叩き方や運手(打ち方の手順)を組み立てる必要があります。
また、全良難易度は「不可が出ないようにすること」だけでは達成できないため、可を出さないようにタイミング精度も非常に重要です。
これにより、同じ譜面であっても全良を目指すプレイヤーにとっては難易度が大きく跳ね上がることになります。
このような性質から、全良難易度はプレイヤーの精度、記憶力、リズム感、体力、集中力といったさまざまな能力をバランスよく求められる、総合力が試される難易度であると言えるでしょう。
最新の全良難易度情報まとめ

2024年以降のアップデートや新曲追加に伴い、太鼓の達人の全良難易度表にも変化が生まれています。
とくに新しい譜面の多くは、従来の難易度に加え、技術的・体力的な負荷が高まる傾向があります。
最近追加された譜面では、「複合リズム」や「変則テンポ」を取り入れた構成が目立ちます。
例えば、一定の速度で叩き続けるだけでは対応しきれないようなリズムパターンが増えており、音符の種類(ドン・カツ)の配置もトリッキーになっています。
これにより、全良難易度としてのハードルも自然と上がっています。
また、最新譜面では「裏譜面(裏鬼)」の採用も増加しており、通常の譜面とは異なる全良攻略が求められます。
裏譜面は隠しコマンドを使って出現させるもので、表譜面と比較して圧倒的に高い難易度を持つケースが多いです。
全良狙いのプレイヤーにとって、こうした最新情報をキャッチアップすることは非常に重要です。
SNSや非公式の難易度表サイトなどを活用して、情報のアップデートを日頃から行うようにすると良いでしょう。
全良難易度ランキングと傾向
太鼓の達人における全良難易度のランキングは、一般的に「どれだけ全良達成が難しいか」を数値や段階で分類したものです。
多くのプレイヤーが参考にしているのは、非公式の「☆10全良難易度表」で、各譜面がS?Fのようにランク付けされています。
上位にランクインしている譜面の傾向としては、リズム変化が激しい・譜面の密度が高い・特殊な叩き方を要求される、といった特徴が見られます。
中でも「ドンカマ2000」や「双竜ノ乱」などの譜面は、フルコンすら難しいとされる中で、全良達成は至難の業とされています。
一方、下位に位置する譜面は、構成が比較的単純でリズムも安定しており、初心者でもチャレンジしやすい内容になっています。
例えば、「タベルナ2000」や「チルノのパーフェクトさんすう教室(裏)」などがそれに該当します。
ランキング表は単なる目安ではありますが、自分の実力に合った譜面を選ぶ参考になるため、全良を狙う際には活用価値が高いと言えるでしょう。
aやssの譜面に見る難関の全良難易度

「a」「ss」といった記号でランク付けされる譜面は、太鼓の達人の全良難易度の中でも特に高難度とされています。
これらの表記は、非公式難易度表などで使われており、「ss」は最難関の譜面群を示すことが多く、「a」はそこに次ぐ難しさを示しています。
これらの譜面の共通点は、単なる速さや物量だけではありません。
たとえば「幽玄ノ乱」や「ドンカマ2000」のようなss譜面は、手順の正確性・リズム認識・高速処理・体力のすべてが求められます。
特にラストでのコンボ崩しを仕掛けてくるような譜面は、1ミスで全良を逃す可能性があるため、非常にシビアです。
一方、「a」ランクに分類される譜面は、全体を通して難所が点在するタイプが多く、緩急の差に対応する柔軟なプレイが要求されます。
たとえば「冷凍庫CJ?嗚呼面太鼓ブラザーズ?」や「Parousia」などが該当し、難所が連続するよりもむしろ、緩い地帯から急に難所へと切り替わる部分に対応できるかが鍵になります。
このような譜面で全良を目指すには、単なる反復練習では不十分であり、譜面研究と自分に合った運手の選定が必要不可欠です。
難関譜面に挑戦する前には、構成の分析や動画研究を行うことで、無駄な試行錯誤を減らすことができるでしょう。
全良難易度表の見方
太鼓の達人の全良難易度表は、曲ごとの「全良達成の難しさ」を把握するための指標として、多くのプレイヤーに利用されています。
これは公式が出しているものではなく、有志によってまとめられた非公式の難易度表であり、プレイヤーの実体験に基づいたランキング形式で構成されています。
難易度表は主に「S」「A+」「A」などのランクで構成され、それぞれが全良達成における技術的・体力的な難しさを示しています。
たとえば、「S」は全良最難関譜面を示し、「A」や「B」はやや易しめの譜面となります。
また、「個人差S」などのカテゴリが用意されていることもあり、譜面の傾向によって難易度の感じ方に個人差が出る点も反映されています。
見方としては、まず自分がフルコンボできている曲を難易度表から探し、その譜面がどのランクにあるのかを確認します。
次に、1ランク上の譜面に挑戦することで、効率的に全良のステップアップを図ることができます。
ただし、難易度表はあくまで目安であり、すべてのプレイヤーに同じ難易度で当てはまるとは限りません。
譜面ごとに得意不得意があるため、自分の感覚と照らし合わせながら活用することが大切です。
特に全良を狙う際は、自分に合った譜面選びを意識することで、モチベーションを保ちながら着実に成果を出せるようになります。
太鼓の達人で全良の難易度の基準を理解する

全良を目指す上で避けて通れないのが、譜面ごとの難易度の違いとその基準を理解することです。
太鼓の達人では、公式の星の数だけでなく、非公式に分類された「全良難易度表」やプレイヤー間で使われる独自用語も存在します。
ここでは、全良を狙う際に役立つ譜面の見極め方や、よく使われる言葉の意味、そして練習のポイントまでを丁寧に解説していきます。
自分に合った難易度や譜面を選ぶために、ぜひ参考にしてみてください。
全良難易度表の塗り方のコツとは?
全良難易度表の「塗り方」とは、太鼓の達人で自分が全良を達成した譜面を視覚的に記録・管理する作業を指します。
この難易度表は通常、プレイヤーが譜面ごとの達成状況をチェックし、進捗管理をしやすくするために使用されます。
塗り方のコツとしては、まず「塗る基準」を明確にしておくことが大切です。
たとえば、単に全良を達成した回数で塗るのか、特定の譜面ランク(例:地力A以上)を優先するのかなど、目的に応じた分類が必要です。
よく見られる方法としては、色分けを活用する方法があります。
たとえば、青は未プレイ、黄色はフルコン、赤は全良など、自分なりのルールで統一すると視認性が向上します。
また、ExcelやGoogleスプレッドシート、画像編集ソフトを活用すれば、データの整理やカスタマイズも容易になります。
ただ、塗りすぎてしまうと逆に進捗が見えづらくなるため、「どこが未達成か」「どこを強化すべきか」がすぐに分かるような塗り方を心がけましょう。
ふよしやpgx とは何か?

「ふよし」「pgx」とは、太鼓の達人のプレイヤー間で使われる特定の俗語や記号のひとつで、主に難易度表や攻略界隈で見かける用語です。
これらは一般的なプレイヤーにはあまり馴染みがなく、初めて目にすると意味が分からないかもしれません。
「ふよし」は一部の譜面名や表現から生まれたスラングで、「不良死」や「不慮死」をもじって使われることもあります。
主に、急な譜面の難所や想定外のミスによってフルコンや全良が途切れてしまう現象を表現するときに使用されます。
「あの譜面、ふよししやすいよね」のように使われます。
一方「pgx」は、特定の難易度帯や譜面構成を示す略称ですが、定まった意味というよりは使うコミュニティや文脈により意味が変化することが多いため、使用されている場所での解釈を確認するのが良いでしょう。
攻略サイトやX(旧Twitter)では冗談交じりに使われることもあり、正確な定義が存在するわけではありません。
これらの言葉は、太鼓の達人に深くハマったプレイヤー同士での共通語として機能しており、理解しておくことでコミュニケーションがスムーズになる場面もあります。
難易度表 星7 星8 星9 星10の違い
太鼓の達人の難易度は、主に星の数(☆)で表されており、☆7?☆10は上級者向けの譜面が揃っていますが、それぞれに明確な違いがあります。
これを理解することで、全良難易度を見極めたり、自分に合った譜面を選ぶ手助けにもなります。
まず☆7は、上位中級者にとってのステップアップに位置づけられ、リズムや複合がやや複雑になり始める段階です。
☆8になると、16分音符や交互処理、体力を要する譜面が増え、精度とスタミナのバランスが求められるようになります。
☆9は、ほとんどの譜面で全良達成に技術的な工夫が必要となり、可を減らすための運手の研究が不可欠になります。
また、局所難や速度変化などが増えるため、譜面の研究量も要求されます。
そして☆10は、最難関クラスに位置づけられており、一部は全国トップクラスのプレイヤーでも全良達成が難しいと言われるほどの譜面が存在します。
譜面の密度・速度・複雑さが飛躍的に上がり、全良のハードルも格段に上がります。
このように、星の数が一つ違うだけでも求められるスキルセットが大きく異なるため、自分の実力に合った星の譜面から挑戦していくことが、効率的な成長につながります。
難易度の種類は?

太鼓の達人には、公式に定められた4つの難易度があります。
それが「かんたん」「ふつう」「むずかしい」「おに」です。
それぞれの難易度はプレイヤーの熟練度に応じて段階的に設定されており、遊びやすさとやりごたえの両方が考慮されています。
「かんたん」は初めて太鼓の達人をプレイする人向けに設計されており、単純なリズムと少ない音符数で構成されています。
「ふつう」は基本的なリズム感と叩くタイミングが身についてきた人が対象で、やや複雑な配置が登場します。
「むずかしい」では、曲ごとに譜面の構成が高度になり、連打や複雑なリズムパターンが含まれるようになります。
プレイ精度や運手の選択も重要になります。
そして最高難易度である「おに」は、複合的な操作・速さ・体力・精度のすべてを求められる譜面です。
さらに一部の「おに」譜面には、隠し要素として「裏譜面(裏鬼)」が存在し、より高難易度の譜面に挑戦できるようになっています。
これらの難易度の種類を理解し、自分のレベルに合った選択を行うことが、上達の第一歩となります。
裏鬼とは?
裏鬼とは、太鼓の達人における特定の曲でのみ出現する、通常よりもさらに難易度の高い「裏譜面」のことです。
正式には「おに」難易度の裏バージョンという位置づけであり、特定の操作によって出現させることができます。
具体的には、曲選択時に「おに」にカーソルを合わせ、右カツを10回連打することで裏鬼が出現します。
選択後は裏譜面でのプレイとなり、終了後は自動的に通常の譜面モードに戻ります。
裏鬼は、単純に音符の数が増えるだけではなく、リズムの変化や配置の複雑さ、手順の難しさ、体力消費などが大幅に上がっているのが特徴です。
たとえば、通常譜面では存在しなかった32分音符の配置が追加されていたり、連続複合が極端に増加していたりします。
全良を狙うには、表譜面以上に研究と反復練習が必要であり、裏鬼はまさに全良難易度を語るうえで避けて通れない存在です。
選曲前に裏譜面が用意されているかをチェックするには、公式サイトの「収録曲リスト」を確認すると確実です。
意識すべき譜面要素

全良を狙う際には、単に「譜面を覚える」だけでは不十分です。
スコアではなく、1打のミスすら許されない状況で求められるのは、譜面そのものの構造や性質を深く理解することです。
特に注目すべきなのは、リズムの「緩急」と「複合構成」です。
速い地帯と遅い地帯が交互に現れる譜面では、体力と集中力の配分が重要になります。
例として、「LECIEL GLISSANDO」や「Parousia」は、密度の差が激しい区間を繰り返し処理する必要があり、途中で気が緩むと即ミスに繋がります。
また、叩き分けが要求される譜面では、12分・16分・24分など異なるタイミングの複合処理をどう対応するかが全良達成の鍵になります。
技術譜面では、局所的な叩き分けスキルや運手の柔軟な変更も求められるため、譜面研究が非常に重要です。
さらに、譜面の「ラスト難所」も意識しましょう。
中盤まで問題なく進めても、ラストに難所が設定されている場合、緊張でミスを誘発しやすくなります。
そのため、実力に合った譜面を選び、全体構成を把握した上で挑むことが重要です。
全良を目指す練習法
太鼓の達人で全良を目指すには、ただひたすらプレイするだけでは効率が悪くなりがちです。
むしろ、戦略的な練習と譜面研究が成果を大きく左右します。
まず基本として、苦手な譜面だけを繰り返し練習するのではなく、自分が「全良に近いスコアを出せている譜面」を選びましょう。
成功体験を積みながら課題点を明確にできるため、モチベーションを保ちやすくなります。
次に重要なのは、譜面ごとの難所をパートごとに分けて練習することです。
特に「ロール処理」や「連打後の切り返し」などは、失敗しやすいポイントなので、1つ1つを運手やテンポに注目して練習しましょう。
また、動画を撮って自分のプレイを見返す方法も効果的です。
可や不可が出る箇所を可視化することで、改善すべき点が明確になります。
加えて、あえて少し難しめの譜面に挑戦しておくと、感覚が研ぎ澄まされ、通常の譜面に戻ったときに余裕を持ってプレイできることもあります。
最終的には「集中力を切らさない持久力」も必要になるため、長時間のプレイや連奏に耐えられる体力作りも含めたトレーニングを意識すると、より安定した全良達成につながるでしょう。
【総括】太鼓の達人の全良で難易度を理解するための総まとめ
最後に本記事の総まとめを紹介したいと思います。