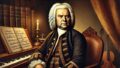インフェルノでギターの難易度と検索してこのページにたどり着いたあなたは、おそらくこの曲に挑戦しようと考えているか、演奏に行き詰まりを感じているのではないでしょうか。
インフェルノは、そのスピード感と迫力あるサウンドで人気の楽曲ですが、ギターで弾きこなすには相応の準備と知識が必要です。
本記事では、初心者でも理解しやすいように、インフェルノに含まれるコードの構造やtab譜の読み解き方、音作りや弾き方のコツを丁寧に解説していきます。
さらに、バッキングとリードの役割の違いや、ベース 難易度とのバランスについても触れながら、演奏全体を高めるための練習方法や楽譜の活用法まで網羅します。
インフェルノは簡単?難しい?そんな疑問に応えつつ、実践に活かせる具体的な解説をお届けします。
■本記事のポイント
- インフェルノのギター演奏に必要な技術とその難易度
- コードやtab譜をもとにした練習の進め方
- 初心者がつまずきやすいポイントと対策方法
- 音作りやリズム表現を含む演奏全体の工夫
インフェルノでギターの難易度と初心者の挑戦ポイント
「インフェルノ」は、その迫力あるサウンドと疾走感で多くのギタリストを魅了していますが、実際に弾こうとすると意外な難しさに直面します。
特にギター初心者にとっては、テンポの速さや複雑なフレーズ、リズムの変化など、乗り越えるべき課題が多く存在します。
ここでは、初心者が「インフェルノ」に挑戦する際に感じやすい壁やつまずきポイントを詳しく解説していきます。
挑戦前に知っておくことで、無理なくステップアップできるヒントが見えてくるはずです。
コード進行と難易度の関係

「インフェルノ」のギター演奏において、コード進行は技術的な難易度と密接に関係しています。
特に初心者にとっては、この曲のコード進行がどういった構造で成り立っているかを理解することで、演奏のハードルを見極めやすくなります。
まず、インフェルノのコード進行には、一般的なポップスやロックとは異なる展開が含まれており、スムーズに弾くためには一定の知識と練習量が必要です。
コード自体は、C、G、Am、Fといった基礎的なものも登場しますが、それに加えてディミニッシュコードやテンションコードといった、やや高度な構成も混ざっています。
これにより、指の押さえ方やコードチェンジのスピードが求められるため、慣れていないプレイヤーにとっては難しく感じられるかもしれません。
また、コードの切り替えタイミングにも注意が必要です。
曲のテンポが比較的速いため、正確なリズムでのコードチェンジが求められます。
テンポに遅れずにコードを押さえるには、フォームの無駄をなくすことが重要です。
このように、コード進行そのものは極端に複雑ではないものの、演奏時のリズム感や運指のスムーズさが難易度を高めています。
そのため、インフェルノを弾きこなすには、コードの理解に加えて、リズム練習やコードチェンジの精度向上が不可欠です。
コード譜を見ながら部分練習を繰り返すことで、徐々に対応力が身についていくでしょう。
tab譜から見る演奏難易度
tab譜(タブ譜)とは、ギター初心者にとって視覚的にわかりやすい楽譜形式ですが、インフェルノのtab譜を見れば、この曲が一筋縄ではいかないことがすぐにわかります。
音符ではなく数字で指板の位置を示すtab譜は、特にピッキングや運指の難易度を正確に把握するのに役立ちます。
インフェルノのtab譜を見ると、早いテンポの中に細かいフレーズが詰め込まれているのが特徴です。
特にリードギターパートには、ハンマリング、プリング、スライド、さらにはスウィープピッキングといった様々なテクニックが盛り込まれており、単に正しいフレットを押さえるだけでは演奏になりません。
こうした技巧が連続することで、物理的なスピードだけでなく、表現力も問われる構成になっています。
さらに、曲全体におけるポジション移動の頻度も高く、指板全体を広く使う必要があります。
これにより、tab譜を見て弾く場合でも視線移動やポジション把握に慣れていないと、演奏中に迷いやすくなります。
つまり、tab譜の情報量が多く、それを読み取りながら正確にプレイするという点で、初心者には高いハードルとなる可能性があります。
これを乗り越えるためには、tab譜を使った練習を単なる模倣ではなく、動きの意味を理解しながら行うことが効果的です。
どの指をどこで使うのか、どのタイミングで技術を入れるのかといった点を意識しながら練習することで、演奏の安定性が増していきます。
このように、tab譜からもインフェルノの演奏難易度は明確であり、練習には計画的なステップが必要です。
始めはスローテンポで一部分ずつ丁寧に練習する方法が推奨されます。
簡単?難しい?初心者の壁とは

「インフェルノ」という楽曲は、ギター初心者にとって一見すると勢いがあってカッコいい曲に思えますが、実際の演奏難易度はやや高めです。
見た目や雰囲気で「なんとなく弾けそう」と感じる人もいるかもしれませんが、細部を見ていくと初心者がつまずきやすい要素が多く含まれています。
まず、テンポの速さが初心者にとって大きな壁となります。
リズムに乗りながらピッキングやコードチェンジを正確に行うには、基礎的な動作が体にしみ込んでいる必要があります。
しかし、演奏経験が浅いと、コードを探している間にテンポについていけなくなることも珍しくありません。
また、使用されているテクニックの多さも難しさの一因です。
インフェルノでは、単純なコード弾きだけでなく、単音リフ、早いフレーズのピッキング、そしてアクセントをつけたバッキングなど、複数の奏法が頻繁に切り替わります。
このような多様な演奏を滑らかにこなすには、相応の練習量と慣れが必要です。
さらに、左手の指の使い方や右手のリズム感も要求されるため、初級者には「曲として完成させる」ことが大きな挑戦になります。
特にリズムキープとアクセントの表現は、基礎練習をしっかり積んでいないと曲の雰囲気を再現することが難しくなります。
このような背景から、インフェルノは初心者にとって「弾けなくはないが、壁が多い曲」と言えます。
まずはスローテンポで練習を始め、部分ごとに細かく分けて取り組むことで、徐々に全体像が見えてくるでしょう。
ギター初心者がインフェルノに挑戦する際の注意点
ギター初心者が「インフェルノ」に挑戦する場合、最初に意識すべきことは、完璧な演奏を急がないことです。
技術的に難しい要素が多いため、無理にテンポや完成度を求めると挫折しやすくなります。
ここでは、初心者が取り組むうえで注意すべき点をいくつか紹介します。
最初に重要なのは、演奏の全体像を把握することです。
曲を部分的に覚えるのではなく、どこでコードが切り替わり、どのセクションでリードやバッキングが入るのかを頭に入れておくと、効率よく練習ができます。
特にリズムの変化やパターンの繰り返しを理解しておくと、混乱せずに取り組めるようになります。
次に、無理に速いテンポで練習しないことも大切です。
インフェルノはテンポが速く、勢いに任せて弾こうとするとミスが増えます。
最初は原曲の半分以下の速さで練習し、ミスなく弾けるようになった段階で少しずつスピードを上げていくのが理想です。
焦らず段階を踏むことで、正確さと安定感を身につけることができます。
さらに、正しいフォームを保つことも注意点の一つです。
力任せに押さえる、あるいは不自然な角度で手首をひねると、長時間の練習で痛みや疲労を引き起こすことがあります。
フォームが崩れると、テクニックも思うように伸びません。
初心者のうちは、鏡を使って自分の姿勢をチェックするのも効果的です。
最後に、練習に行き詰まったときは、原曲を聴き込むことをおすすめします。
フレーズの雰囲気やリズム感を身体に染み込ませることで、譜面だけでは見えない「ノリ」や「勢い」が自然と表現できるようになります。
耳と手を連動させる練習を重ねることが、曲を完成させる一歩です。
このように、インフェルノに挑戦する際は、演奏の計画、練習スピード、正しいフォーム、そして耳からのアプローチという複数の視点から取り組むことが大切です。
焦らず着実にステップを踏んでいけば、少しずつ自信がついてくるでしょう。
インフェルノでギターの難易度を左右する演奏要素
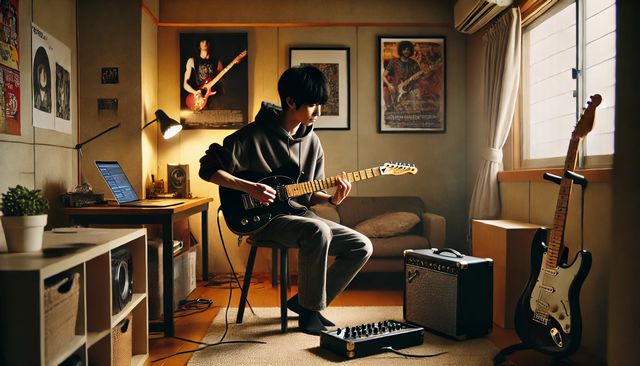
インフェルノのギター演奏において、難易度を大きく左右するのは単なる指の動きだけではありません。
音作りや演奏技術、リズム感など、演奏に関わる要素が複雑に絡み合っています。
これらを理解し、的確に対処することで、難しいと感じていたフレーズも驚くほどスムーズに弾けるようになる可能性があります。
ここでは、演奏を深めるためのポイントや、上達につながる実践的な練習のヒントを詳しく解説していきます。
音作りとその再現方法

インフェルノをギターで演奏するうえで、「音作り」は曲の雰囲気を決定づける非常に重要な要素です。
どれだけ技術的に正確に弾けたとしても、音の質感が原曲とかけ離れていれば、聴き手に与える印象も大きく異なってしまいます。
まず、インフェルノのサウンドは、攻撃的かつタイトなディストーションが基盤になっています。
使用するアンプは、ハイゲインタイプのものが適しています。
エフェクターでは、オーバードライブやディストーションペダルを使って歪みを加え、EQ(イコライザー)で中域をやや強調すると、原曲に近い厚みのある音が得られます。
加えて、インフェルノでは音の「キレ」も重要です。
そのためには、リバーブやディレイを控えめに設定し、ミュート気味のバッキングでも音がぼやけないようにする必要があります。
ピッキングの強さや右手の位置によっても音の輪郭は変わるため、音作りは単なる機材設定にとどまらず、奏法との組み合わせも意識しなければなりません。
再現性を高めるためには、まず原曲をヘッドホンでよく聴き込み、どのパートでどんな音が使われているのかを丁寧に分析することが大切です。
録音環境や機材が異なっても、ニュアンスを意識することで近い雰囲気を作ることは可能です。
このように、インフェルノの音作りは「機材」「奏法」「耳」の3つの視点でアプローチすることがポイントになります。
音そのものが演奏の魅力を大きく左右するからこそ、演奏前の音作りにも丁寧に時間をかけて取り組みたいところです。
弾き方におけるリズムとテクニック
インフェルノのギターパートには、スピード感のあるリズムと多様なテクニックが凝縮されています。
ただ単に譜面通りに弾くだけでは曲の勢いやニュアンスを表現しきれないため、リズムの感覚と演奏技術のバランスが問われます。
この曲のリズムの特徴は、タイトな8ビートを基調としながらも、細かいシンコペーションやアクセントの位置が複雑に絡み合っている点にあります。
そのため、一定のテンポでメトロノームに合わせて練習するだけでなく、曲のノリやグルーヴ感を身体で感じ取ることが重要になります。
リズムを「感じる」ことで、機械的にならず、自然な演奏ができるようになります。
テクニック面では、ハンマリング、プリングオフ、スライド、ピッキングハーモニクスなど、ロック系プレイヤーにとって基本とも言える技法が随所に登場します。
ただし、これらを単独で練習するのではなく、インフェルノのフレーズの中で「どう機能しているか」を意識して使いこなすことが重要です。
特に速いパッセージでは、指の力を抜いた状態でスムーズに運指できるようになるまで、繰り返し練習を重ねる必要があります。
また、ピッキングも重要な要素です。
リズムを保ちながら正確なアタックを出すためには、ダウンピッキングとオルタネイトピッキングの使い分けを意識すると安定感が増します。
ここでも、単に弾くのではなく、音の粒を揃えるような丁寧な演奏が求められます。
このように、インフェルノの弾き方は「リズム感」と「演奏技術」が密接に結びついています。
まずはゆっくりとしたテンポで正確にフレーズをマスターし、そこから少しずつテンポアップしていく方法が効果的です。
細かい部分に気を配りながら積み上げていくことで、完成度の高い演奏に近づいていくでしょう。
ベースの難易度とギターとの連携

インフェルノのベースパートは、派手なソロこそないものの、曲全体の土台を支える非常に重要な役割を担っています。
演奏難易度としては中級者向けといえるレベルで、一定のリズム感と運指の安定性が求められます。
ベース特有の「目立たないがミスが許されない」立場であることを意識して取り組む必要があります。
この曲のベースは、ドラムと連動してタイトなリズムを形成しており、ギターリフに合わせてテンポ良く動くフレーズが多く登場します。
例えば、8ビートを刻む中に16分音符の動きを差し込んでグルーヴを生み出す場面もあり、一定の演奏技術と集中力が求められます。
さらに、ミュート奏法やスライドを効果的に取り入れることで、より立体的なサウンドを演出することができます。
ギターとの連携面では、特にバッキングパートとのタイミングが重要です。
リズムのズレが生じると、曲全体が散漫な印象になってしまうため、ギターのリズムを正確に聴き取り、それに合わせたタイム感で弾くことがポイントです。
また、ベースライン自体がギターリフとハモるように構成されている部分もあるため、音程の正確さと表現力も意識する必要があります。
このように、インフェルノのベースは単なる伴奏ではなく、ギターとドラムの橋渡しとして機能しているポジションにあります。
演奏を安定させるには、個人練習だけでなく、ギターと合わせたアンサンブル練習を重ねることが不可欠です。
リズムを「感じる耳」と「支える手」の両方が育って初めて、この楽曲のベースの魅力が発揮されるでしょう。
バッキングパートの特徴と難易度

インフェルノにおけるバッキングパートは、単なる背景ではなく、曲のエネルギーと躍動感を支える重要な要素です。
多くの場合、バッキングはコードを押さえてリズムを刻むシンプルな役割と見られがちですが、この曲ではそうした常識が通用しません。
テンポの速さ、リズムの変化、そして精密なタイミングが要求されるため、実際の難易度は決して低くありません。
このパートで特に特徴的なのは、単純なストロークではなく、スタッカート気味のカッティングやミュートが多用されている点です。
そのため、右手と左手の連携が求められ、片方だけに意識を集中しているとリズムがズレたり、音が濁ったりする原因になります。
また、フレーズごとに求められるタッチの強弱も異なるため、細かなダイナミクスのコントロールが必要です。
さらに、バッキングといえどもコードチェンジのスピードが速く、精密な運指が求められる場面が多くあります。
特にパワーコードやバレーコードが頻繁に登場し、それらを瞬時に押さえる指の柔軟性と筋力が不可欠です。
加えて、バッキング中に単音リフを織り交ぜる構成もあり、単純にコードだけを弾いていればよいという曲ではありません。
インフェルノのバッキングは、単調な繰り返しではなく、リードパートと呼応しながらリズムのキレを保ち続ける役割を持っています。
そのため、難易度としては中から上級者向けといえる内容です。
はじめはテンポを落として練習し、右手と左手の動きを個別に確認しながら、少しずつ正確性とスピードを高めていくとよいでしょう。
こうした背景から、バッキングといえども気を抜けないのがインフェルノの特徴です。
安定した演奏ができれば、曲全体の迫力が一段と増し、演奏者としての満足感も高まるはずです。
リードパートの演奏ポイント

インフェルノのリードパートは、曲の中でもとりわけ華やかで、技術的な見せ場が集中するセクションです。
速いフレーズや複雑なテクニックが多用されており、演奏者のスキルが如実に問われるパートでもあります。
そのため、単にフレットを押さえるだけでなく、「どう弾くか」「どんな音を出すか」が非常に重要になってきます。
まず押さえておきたいのは、リズムと音符の長さをしっかりと把握することです。
インフェルノでは、8分音符と16分音符が組み合わされた高速フレーズが多く、テンポに遅れたり、走ったりするとフレーズ全体のまとまりが崩れてしまいます。
したがって、メトロノームやドラムマシンを使ってリズムトレーニングを継続することで、安定した演奏が可能になります。
さらに、テクニック面ではオルタネイトピッキングやスライド、ハンマリング・オン/プリング・オフが頻繁に登場します。
これらをスムーズに繋ぐためには、ピッキングの角度や指の動きを最小限に抑える意識が必要です。
特にスライドの位置やタイミングがずれると音程やフレーズの流れに違和感が生じるため、練習時には指の位置や力加減にも気を配りましょう。
また、リードパートでは単に速さや正確さだけでなく、「表現力」も問われます。
フレーズの始まりに軽くアクセントを加えたり、音を伸ばす箇所でビブラートをかけるなど、細かなニュアンスを丁寧に演奏することで、音楽としての魅力が格段に高まります。
これらはTAB譜だけではわかりにくいため、原曲を繰り返し聴いて耳で感じることも大切です。
このように、インフェルノのリードパートは、正確さ・スピード・表現力の3つが揃って初めて完成度の高い演奏が可能になります。
細部にこだわった地道な練習が、自信につながる最も確実な方法です。
楽譜を活用した練習方法

楽譜を効果的に使うことは、インフェルノのような複雑な構成を持つ楽曲を習得するうえで大きな助けになります。
ただし、ただ眺めるだけでは上達に直結しないため、活用の仕方に工夫が必要です。
ここでは、具体的な楽譜活用法を解説します。
まず前提として、楽譜には大きく分けて「五線譜」と「TAB譜」があります。
インフェルノのようなロック系の曲ではTAB譜の使用が一般的ですが、リズムやフレーズの細かなニュアンスを理解するためには、可能であれば五線譜と併用することが理想的です。
リズム譜が読めると、音の長さや入りのタイミングが明確になるため、練習効率が格段に向上します。
次に、楽譜を「いきなり最初から最後まで」弾こうとするのではなく、セクションごとに分けて少しずつ取り組むことが大切です。
例えば、イントロ、バッキング、リードソロ、アウトロといった形で楽曲を細分化し、それぞれを確実にマスターするようにしましょう。
特にリズムが難しいパートや運指が複雑な箇所は、繰り返し重点的に練習することで、スムーズな演奏につながります。
また、練習の進度を記録していく方法も効果的です。
日ごとにどのパートを何回練習したか、どのテンポでミスが出やすいかをメモしておけば、苦手部分の克服や練習の優先順位づけに役立ちます。
こうして客観的に自分の進捗を把握することが、モチベーション維持にもつながります。
さらに、楽譜に自分用のメモを書き込むことも推奨されます。
どの指を使うか、ピッキング方向、アクセントの位置など、演奏中に忘れがちなポイントを書き加えておくと、視覚的にも整理されて演奏に集中しやすくなります。
このように、インフェルノの楽譜はただのガイドではなく、演奏力を高めるためのツールとして積極的に活用すべき存在です。
曲を理解し、効率的に練習するための道しるべとして、楽譜を味方につけることが上達への近道になります。
演奏を深めるための解説動画の活用
インフェルノのようにスピード感とテクニカルな要素が詰まった楽曲を習得するには、解説動画の活用が非常に有効です。
楽譜やtab譜だけでは伝わりにくい手の動きやニュアンスを、視覚と聴覚の両方から理解できるのが動画の最大のメリットといえます。
まず、信頼できる解説動画を選ぶことが第一のポイントです。
内容が正確で、演奏技術の高い講師が丁寧に説明しているものを選ぶと、無駄なく学べます。
特に、パートごとに分割されている動画は、自分のペースで練習しやすいため初心者にもおすすめです。
タイトルに「スロー再生」「初心者向け」「パート別解説」などの表記があるものを探すと、より実践的に活用できます。
動画を見る際は、ただ真似して弾くのではなく、「なぜその指使いをしているのか」「ピッキングの角度はどうなっているか」「リズムの取り方に工夫があるか」など、細かな部分に意識を向けることが大切です。
これは一見地味な作業に思えるかもしれませんが、こうした観察力が上達を加速させる鍵となります。
また、演奏を覚える段階では再生速度を落として、フレーズの細部まで確認しながら練習することが効果的です。
YouTubeなどでは再生速度を調整できるため、特に早いパッセージの習得に役立ちます。
耳だけでは捉えづらい箇所も、動画なら動きと音が連動しているので理解しやすくなります。
このように、解説動画は単なる模倣の手段ではなく、演奏の理解を深めるための教材です。
正しい使い方を意識すれば、短時間で効率よくスキルを伸ばすことが可能になります。
自分の苦手な部分に特化した動画を選び、ポイントを絞って視聴することで、練習の質も格段に高まるでしょう。
演奏を成功させるための練習計画

難易度の高い曲に取り組む際、事前に練習計画を立てることは、効率よく上達するための重要なステップです。
インフェルノのように速いテンポと多彩なテクニックが求められる楽曲では、場当たり的に練習するのではなく、段階的に目標を設定することで挫折を防ぎ、確実な成長につなげることができます。
最初のステップは、楽曲全体の構成を把握することです。
イントロ、Aメロ、サビ、間奏、リードソロ、アウトロといったように、セクションごとに分けて曲を理解します。
この段階ではまだ弾けなくても構いません。
曲の流れを頭に入れておくことで、どの部分を優先的に練習すべきか判断しやすくなります。
次に、各セクションを難易度別に分類し、簡単なパートから取り組みます。
例えば、コードストローク中心のバッキング部分は早めに習得し、リードパートや速いフレーズなどの難所は、時間をかけて少しずつ習得していく方が効率的です。
一日で全体を仕上げようとせず、1週間単位、あるいは日ごとに「このフレーズをスムーズに弾けるようにする」といった具体的な目標を設定しましょう。
また、テンポ管理も計画の重要な要素です。
初めから原曲のスピードで弾くのではなく、メトロノームやテンポ調整アプリを使って、自分のレベルに合ったテンポからスタートします。
正確に弾けるようになってから徐々にスピードを上げていく方法は、演奏の安定性と自信につながります。
さらに、1回の練習時間を短く区切ることも有効です。
集中力が持続しやすくなり、フォームの乱れや無理な力みを防ぐことができます。
20から30分ごとに休憩を入れることで、筋肉の負担を減らしながら効率的な練習が可能になります。
このように、練習計画を立てることで、単に「弾けるようになる」だけでなく、「安定して、表現豊かに演奏する」ことが目指せるようになります。
ステップごとの目標を明確にして、焦らず一歩ずつ取り組む姿勢が、結果的にもっとも早く完成に近づく方法です。
【まとめ】インフェルノでギターの難易度について
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。