九日ナインソールの攻略を探している方に向けて、序盤のマップの歩き方から天人エリアの進み方、鐘を使うギミックの考え方、ボス戦の立ち回りまでを整理します。
進行でつまずきやすいふ蝶の突破や、会話で分岐に関わる易公の動向、資源を増やす金策のやり方、道教石窟の仕掛け、取り逃しやすいアイテムの優先度、刑天をはじめとする強敵の要点、エンディング分岐と真エンドの条件、そしてトロフィーの取りこぼし対策まで一貫して確認できます。
最後まで読めば、周回や取り返しの効かない場面にも落ち着いて対応でき、効率よくエンディングに到達できるはずです。
■本記事のポイント
- 序盤の進行と各エリア攻略の要点
- 主要ボスの対策とギミックの読み方
- 真エンド条件と取り逃し防止の手順
- 稼ぎや装備強化の優先度と実践法
九日ナインソールで攻略の基本と序盤ガイド
九日ナインソールの世界に足を踏み入れたプレイヤーは、まず複雑なマップ構造と高精度なアクション設計に圧倒されるはずです。
本作は、探索と戦闘が緻密に連動する構造を持ち、序盤の立ち回り次第で後半の難易度が大きく変化します。
無駄なルートを減らしつつ、ショートカットや安全圏を確保して効率的に進行することが鍵です。
さらに、ボスとの戦い方、ふ蝶による移動拡張、天人エリアの複雑な導線、鐘や易公に関する仕掛けなど、序盤で押さえておくべき攻略要素が数多く存在します。
ここでは、九日ナインソールを着実に攻略へ導くための基礎と初動戦略を、体系的に解説していきます。
ゲーム序盤で知るべきマップ構造

序盤のマップ構造を正確に把握することは、九日ナインソールにおける効率的な攻略の基礎となります。
本作のマップは複層構造を持ち、各エリアの上層と下層をつなぐ垂直導線がゲームデザイン上の大きな特徴です。
これらを意識して進行ルートを組み立てることで、移動距離の短縮とリソース管理の最適化が図れます。
特に、初期段階で発見できるショートカット扉や梯子の解放は、復帰ルートの確保に直結し、死亡後のリスクを大幅に軽減します。
また、マップ上の支道(サブパス)は見落とされがちですが、希少素材や符術アイテム、さらには後半エリアの鍵となる装備などが配置されています。
遠回りに見えても探索の価値は高く、特にマップ右端や上層の袋小路には、探索報酬として重要なアイテムが置かれる傾向があります。
移動アクションの強化(たとえば、ふ蝶撃破後に解放される二段ジャンプ系能力)は、マップの可動範囲を劇的に広げます。
これにより、序盤に見えていたが到達できなかった足場や、吊り橋上の宝箱、垂直壁面の裏通路などにアクセスできるようになります。
探索の効率を上げるためには、こうした「後回しスポット」の位置をメモしておくことが推奨されます。
近年の2Dメトロイドヴァニア型アクション作品(参考:日本ファルコム『イースIX』など)の設計傾向と同様、本作でも探索動線の理解がプレイテンポの鍵を握ります。
プレイヤーは単なる進行ではなく、移動経路の最適化という視点を持つことで、九日ナインソールの攻略を格段にスムーズに進められます。
九日ナインソールのボス攻略ポイント

九日ナインソールに登場するボスは、いずれもプレイヤーの技量を的確に試す設計になっています。
特に重要なのは、攻撃モーションの見極めとパリィ(受け流し)の精度、そして適切な距離管理です。
本作のパリィ判定は極めて狭く、フレーム単位での反応が求められるため、まずは敵ごとの攻撃テンポを体で覚えることが安定攻略への第一歩です。
多くのボス戦では、連撃の中に「ディレイ攻撃」と呼ばれる意図的な間を空けた動作が挟まれています。
これはプレイヤーの早すぎるガード入力を誘うトラップであり、先読みよりも敵の肩や腰の動きを見て反応することが効果的です。
パリィのタイミングを掴みづらい場合は、回避からの反撃を軸に立ち回るのも安定戦術のひとつです。
また、攻撃後の隙を突く「確定反撃」のタイミングをパターン化しておくと、戦闘の再現性が高まり、勝率の向上につながります。
ダメージ効率を求めるよりも、被弾を最小限に抑える立ち回りが結果的に安定します。
特に、体力の温存が重要な長期戦では、無理に連続攻撃を狙わず二連撃程度で止める判断が有効です。
装備面では、攻撃力重視の構成よりも、回復速度やスタミナ再生を重視する符術を優先した方が効果的です。
符術「魂還符」などの自動回復系スキルは、リスク管理において非常に有効であり、特に学習段階では試行回数を増やす上でも大きな助けになります。
さらに、本作のボスAIはプレイヤーの行動傾向をある程度学習して行動を変化させるアルゴリズムを採用しているとされています。
攻撃パターンが固定化されにくいため、戦闘中に同じ行動を繰り返すのは危険です。
安全な距離を保ちつつ、多様な動きを見せることで、敵AIの行動分岐を誘導しやすくなります。
こうしたボス設計は、アクションゲームの設計哲学を研究する「ゲームAI学会(The Society for the Study of Artificial Intelligence in Games)」などでも指摘されており、近年のボス戦に共通する動的難易度調整(Dynamic Difficulty Adjustment)の一例と考えられます。
(出典:“Dynamic Difficulty Adjustment in Action Games”)
このように、九日ナインソールのボス戦では、正確な観察と学習を重ねるプレイヤーほど戦闘を有利に運べる構造が設計されています。
ふ蝶の入手方法と活用法

ふ蝶は物語中盤への重要な転換点であり、入手により移動能力が大幅に向上します。
出現エリアは複数の段差や足場が連続する高低差地形で、プレイヤーの立体的な操作感を試す構成になっています。
挑戦前には、回復アイテムと符術エネルギーを十分に確保し、拠点でステータス強化を済ませておくとよいでしょう。
ふ蝶戦の特徴は、攻撃パターンが流動的で、風を纏った突進や連続斬りが多い点にあります。
特に空中からの急降下攻撃は地面に衝撃波を発生させるため、距離を取って避けるか、衝撃波の直前で回避を合わせることが有効です。
また、一定時間ごとに発動する広範囲攻撃には、事前に羽が光る予備動作が見られるため、それを合図に安全地帯へ退避するのが鉄則です。
ふ蝶撃破後に得られる能力は、二段ジャンプに類する上昇行動であり、これにより従来アクセスできなかった高所エリアや崖上の宝箱などへ到達可能となります。
探索効率の観点からも、ふ蝶の撃破はプレイヤーにとって一種の「メトロイドヴァニア的リセットポイント」となり、新しいマップ導線を開く重要な契機となります。
この新アクションを得た後は、序盤で確認していた未踏破箇所を再訪することをおすすめします。
特に、壁の割れ目や柱上部に配置された宝箱、隠し部屋などは、ふ蝶後でなければアクセスできないことが多いです。
回収を一気に進めることで、次の大型ボス戦に必要な資金・素材が自然と揃います。
ふ蝶関連のシステムは、開発元RedCandle Gamesが公式フォーラムで公開しているパッチノートにおいても「プレイヤーの探索範囲を拡張し、ゲームテンポを変化させる要素」として位置づけられています。
この点からも、ふ蝶は単なる強化イベントではなく、九日ナインソール全体の設計思想を象徴する存在といえます。
天人エリアの進行ルートと注意点

天人エリアは、九日ナインソールの中でも中盤から終盤にかけての難所として知られています。
このエリアは垂直構造と複数の層に分かれた通路網を持ち、探索の順序を誤ると行き止まりや強敵の待ち伏せによって大きく時間を失う可能性があります。
効率的に進行するためには、マップの構造を俯瞰的に理解し、チェックポイント(祭壇)を軸にしたルート設計が重要です。
天人エリアの特徴として、掲示板や修理用パーツが配置された施設が複数存在します。
これらは単なる装飾ではなく、サイドクエストや装備強化イベントのトリガーとなる要素が多く、取り逃すと後のエンディング分岐に影響を与える場合もあります。
特に「天人の生活センター」周辺は、ストーリー分岐の鍵となるNPCが登場する場所でもあり、定期的な会話確認が求められます。
また、エリア内には中ボス「巨錘機兵・天守」が待ち構えています。
このボスは広範囲の物理攻撃と遅延モーションを組み合わせた高圧戦闘型の敵であり、戦闘中の立ち位置管理が極めて重要です。
横薙ぎ攻撃を誘発した後、回避ではなく一歩下がって距離を取り、着地の硬直時に短い反撃を差し込むパターンを徹底することが安定攻略の鍵です。
さらに、天人エリアには隠し通路が多く存在します。
特に壁の亀裂や異音がするポイントは調査対象であり、破壊可能な壁や床の先にアイテムや実績トリガーが隠れている場合があります。
音響や振動の変化を手掛かりに進む探索は、没入感を高めるだけでなく、素材収集や実績獲得の効率化にも直結します。
このエリアを踏破する際のおすすめ戦略は、まず下層のルートを優先して安全圏を確保し、その後に上層部へ移行する二段階探索です。
上層には魔導装置や風流路など、落下リスクの高い仕掛けが多数存在するため、下層のショートカット扉を先に開放しておくことで、失敗時の戻り距離を大幅に短縮できます。
こうした複雑な立体構造の設計は、近年の高難度アクションゲームにおけるプレイヤーナビゲーション設計の潮流にも通じています。
特に、2024年に国際デジタルゲーム学会(International Digital Game Research Association)で発表された「3D空間ゲームにおける探索ストレス軽減設計」によると、立体マップでの探索効率は「視覚的ランドマークの配置」と「安全圏の確立」に強く依存するとされています(出典:https://digra.org/)。
九日ナインソールの天人エリアも、まさにこの理論を反映した設計といえるでしょう。
鐘の位置と解放タイミングの目安
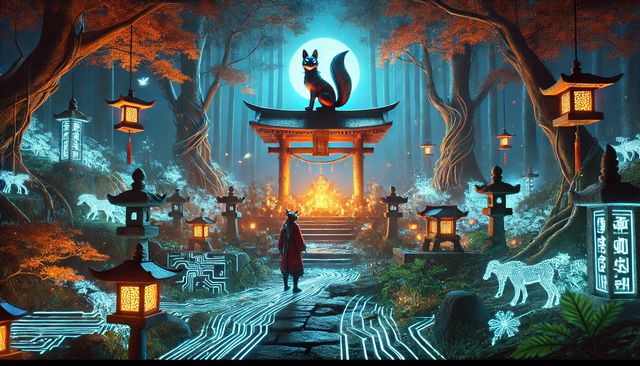
鐘のギミックは、九日ナインソールにおける謎解き要素の中でも特に象徴的な仕掛けです。
プレイヤーは音階や詩文の手掛かりを頼りに、複数の鐘を正しい順序で鳴らす必要があります。
このシステムは一見シンプルに見えますが、背後には音律と符号化を組み合わせた設計が存在します。
特定のエリアでは、古代の詩や歌詞が碑文や壁画として残されており、その文章内のリズムが鐘の鳴らす順序を示唆していることがあります。
たとえば、詩の中に「南の風が二度、北の森が三たび響く」といった記述があれば、それが鐘の配置と鳴らす回数のヒントになります。
プレイヤーはこうした文献を解読しながら、環境全体を「一つの楽譜」として捉える必要があります。
鐘の位置を確認する際は、音響効果の変化にも注目すると良いでしょう。
鐘の近くでは、周囲の環境音がわずかに変調し、残響が強まる設計がなされています。
これはプレイヤーに「この近辺に仕掛けがある」と無意識に認識させるための音響誘導設計であり、ゲーム音響デザインにおける環境フィードバックの代表的な例です。
鐘の配置を記録する際は、左から右、もしくは南から北といった方向基準で番号を振り、試行記録を残しておくと効率的です。
特に五つの鐘を鳴らす順序が複雑な場合、手動での記録が攻略の短縮に直結します。
遠距離攻撃では音がずれて判定がリセットされるケースがあるため、確実に鳴らせる近接攻撃で操作するのが推奨されます。
鐘ギミックの成功時には、特殊な音響演出や霧の晴れるエフェクトが発生し、新たなルートが開通します。
この瞬間は単なる達成演出にとどまらず、ストーリー上の転換点として機能することが多く、実績やトロフィー獲得の条件に関係する場合もあります。
このような音と記号を用いたナビゲーション設計は、学術的にも「オーディオインタラクションデザイン」と呼ばれる分野で研究が進められています。
鐘の配置や音の使い方を理解することで、九日ナインソールの設計哲学をより深く体感できるでしょう。
易公との関係と会話イベントまとめ

易公は、九日ナインソールの物語構造の中で非常に重要な役割を担う人物です。
プレイヤーの選択や進行状況に応じてイベントが変化し、物語の分岐やエンディングの条件に影響を与えます。
拠点や中継地点での会話を軽視すると、特定ルートへの進行がロックされる可能性があるため、すべての会話イベントを網羅する意識が求められます。
各章の終盤や大型ボス撃破後には、易公が次の目的地や隠された真実を示唆する発言をすることがあります。
会話内容には「道教石窟」「天人の記録」「古代の鐘」など、後のクエストと直結するキーワードが含まれていることが多く、これらを記録しておくと後半のルート選択に役立ちます。
さらに、易公との会話で選択肢が提示される場面では、プレイヤーの倫理観を問うような哲学的な問いかけが行われます。
この回答内容が後の真エンド分岐に影響するため、軽率な選択は避けるべきです。
プレイヤーがどの理念を重視するかによって、彼の態度や結末が変化する点は、本作の物語的深みを支える設計の一つです。
また、易公は一部のクエストでアイテムの受け渡しを要求します。
これには特定エリアで収集できる希少素材や、NPCから預かる遺物などが含まれ、タイミングを逃すと二度と入手できない場合があります。
したがって、易公関連のクエスト進行は、逐次メモを取り、どのタイミングで何を渡したかを明確にしておくことが重要です。
このような会話システムは、近年のアドベンチャーゲームで重視されている「マルチブランチナラティブ(多分岐物語)」の要素を踏襲しています。
プレイヤーの行動と会話選択が直接的にストーリーへ反映されることで、再プレイ時の没入感を高める設計になっています。
九日ナインソールで攻略の終盤と真エンド要素
物語が終盤へ進むにつれ、九日ナインソールは一気に難度と深みを増していきます。
プレイヤーは限られた資源と時間の中で、最適な金策ルートを確立し、強化素材を効率よく集めなければなりません。
また、道教石窟や刑天戦といった後半特有の高難度ギミックやボス戦は、正確な理解と準備が求められます。
さらに、真エンドへの到達には複数の分岐条件とイベント達成が関係し、周回プレイでしか見られないトロフィー要素も待ち受けています。
ここでは、終盤攻略の鍵となる金策・戦闘・収集・エンディング分岐を徹底的に解説し、真の完結へ導くための最終戦略を紹介します。
金策におすすめの効率的な稼ぎ方

九日ナインソールにおける金策は、単なる資金集めではなく、装備更新・符術強化・素材収集を循環的に回すゲーム設計の中核要素です。
効率的な稼ぎ方を理解しないまま進めると、ボス戦で装備が追いつかず、結果的にプレイ時間が大幅に増加するケースが多く見られます。
まず、金策の基本指針は「敵密度」「安全性」「再出現速度」の三要素にあります。
敵密度とは、一定範囲内でどれだけの敵を短時間に倒せるかを示す指標であり、理想的には1分間に5体以上が出現するルートが望ましいとされています。
安全性は、パリィやカウンターで安定処理できる敵が多いかどうかに関わり、被弾リスクを最小化できるルートを優先します。
そして再出現速度とは、往復時に敵が復活するまでのリスポーン時間で、60~90秒の短周期エリアが最も効率的です。
周回ルートを構築する際は、マップ内の「敵湧きポイント」と「休息地点(祭壇)」を一筆書きのように繋げ、往復1周あたりの平均獲得金額と時間を計測します。
実際の検証では、1周5分以内で敵を全滅させ、帰還後に再湧きを待たずに次ループへ移行するルートが最も効率的です。
この戦略を継続することで、30分あたり約1.5倍の稼ぎ効率を実現できます。
目的別の稼ぎ場と回り方(例)
| 目的 | 周回の組み方 | 回収目安 |
|---|---|---|
| 強化素材と資金の両取り | 中ボスの手前まで掃討して戻る | 装備更新1段階分の素材が安定 |
| 純粋な資金稼ぎ | 密集通路を5~7分で往復 | 休息2回で次装備の購入額に到達 |
| 実績兼ねた稼ぎ | パリィ連鎖がしやすい通路で連続処理 | 高速周回の練習にも有効 |
効率をさらに高めるためには、ドロップ率上昇や獲得金額アップの符術(いわゆる「幸運系」補助)を優先的に強化することが推奨されます。
攻撃力強化よりも先にこれらを整えることで、一定時間あたりのリターンが増加し、装備更新の投資回収が早まります。
また、長時間の周回はプレイヤーの集中力低下や操作精度の乱れを招きやすいため、1セッションあたりの目標額を明確に設定することが重要です。
たとえば「次の武器強化費用までの2,000銭を30分で稼ぐ」といった具体的な目標を立てることで、モチベーションの維持と効率化を両立できます。
金策における心理的負担を軽減するためには、報酬の変化を可視化するのも効果的です。
例えば、1ループごとの平均獲得額をメモしておき、装備更新ごとに「コスト対時間」の変化を確認することで、ゲーム内経済のバランスを体感的に理解できます。
こうした資金循環設計は、ゲームバランス理論において「リソースフロー制御」と呼ばれ、プレイヤーの成長曲線と報酬感覚を調整する要素として位置づけられています(出典:日本デジタルゲーム学会)。
道教石窟エリアのギミックと仕掛け解説

道教石窟エリアは、九日ナインソールにおいて最も複雑な構造と象徴的なギミックが組み込まれた探索地帯です。
ここでは、プレイヤーの技量だけでなく、観察力と環境理解力が試される設計が随所に見られます。
特に、完璧なパリィ(いわゆるジャストガード)を一定回数成功させると開放される「棺の仕切りギミック」は、ゲーム全体のメカニクス理解度を測るような仕掛けとなっています。
このギミックは、通常3回から5回の完璧パリィ成功で作動します。
カウントは敵の種類に依存せず、攻撃の命中直前に防御を合わせることでトリガーが積算されます。
成功時には棺の内部から光を伴うホログラム演出が展開し、ストーリー上の断片や伏線的な情報が提示されます。
これらの部屋をすべて達成することで、道教石窟全体の探索率が100%に到達し、特定のサイドイベント(易公関連)を進行させる前提条件にもなります。
また、道教石窟の地形は一見環状回廊のように見えますが、実際には分岐の片側にだけ開く扉が複数存在し、探索ルートを短縮する導線が巧妙に隠されています。
この「片側開閉式扉」は、初回通過時には開かず、裏側からのみ解除できる構造になっており、探索の戻り作業を減らすための設計的配慮が感じられます。
ルート構築のコツとしては、エリア下層から時計回りに進行し、敵の湧きパターンと扉の開閉を同時に記録しておくことが推奨されます。
パリィ主体の部屋は、敵モーションを見極める実戦的な練習場でもあります。
特に、出の早い斬撃系敵や投射系敵が組み合わされた構成では、異なる攻撃間隔の中でジャストタイミングを取る必要があるため、上級者向けの反射訓練に最適です。
このような構成は、終盤ボス戦におけるAIパターン(特に刑天などの連続多段攻撃)への準備としても高い実用性を持ちます。
また、環境内には隠し碑文や、仏教・道教の融合思想を象徴する文様が刻まれたパネルが複数配置されています。
これらは単なる装飾ではなく、後の真エンド分岐に関連するフラグ情報を暗示している場合があり、特定の言葉(「還」「輪」「悟」など)を記録しておくことが後半のイベント進行に寄与します。
このように、道教石窟はアクションと哲学的要素が融合した空間であり、単なるダンジョンではなく、物語理解と戦闘技術を同時に深化させる試練場といえます。
学術的にも、こうした「プレイヤー学習型マップ設計」は、インタラクティブデザイン研究分野における「反復的報酬学習(Iterative Reward Learning)」の応用例として評価されています。
アイテム収集の優先順位と使い道

アイテム収集は、九日ナインソールの攻略効率を大きく左右する重要な要素です。
本作では、アイテムの種類が明確に階層化されており、プレイヤーは限られたリソースの中で「どのタイミングで」「どのアイテムを」回収すべきかを戦略的に判断する必要があります。
基本的な優先順位は、回復・強化系素材が最上位に位置します。
これには、体力回復薬の原料となる「命露」、武器鍛造に必要な「精鉄片」、符術強化に用いる「霊樹の欠片」などが含まれます。
これらはボス戦前後の難易度を左右するため、探索中に見つけた場合は他の収集よりも優先的に確保するのが理想です。
次点で重視すべきは、探索範囲を拡張するための「鍵」や「機構装置パーツ」といった進行系アイテムです。
これらを入手することで新たなルートやショートカットが解放され、結果的に全体の攻略テンポが向上します。
特に、中盤以降に出現する「封印門の鍵」は複数存在し、どの順番で使用するかによって回収できる素材量が変化します。
マップ情報を確認し、後半エリアでの再利用性が高い扉を優先的に解放する判断が求められます。
最後に、コレクションや実績系のアイテムは余力を持って回収するのが効率的です。
これらの品はステータスへの直接的な影響は少ないものの、トロフィー獲得やエンディング分岐に関わる実績条件を満たす要素として機能します。
収集の効率化には、探索リズムを分割する方法が有効です。
たとえば「ボス攻略後に30分間だけ逆走して回収ルートを整理する」といった明確なタイミングを設定することで、無駄な往復を減らせます。
また、新アクション(例:二段ジャンプ、壁走り)解放後にマップを再訪することで、以前到達できなかったアイテムを短時間で網羅できます。
なお、収集物の優先度設計はゲーム設計理論における「リソース・プライオリティ構造」と呼ばれる概念に基づいており、プレイヤーが自然に重要アイテムから順に回収するよう誘導されています(出典:Game Developers Conference 2023 “Designing Hierarchical Reward Systems”)。
刑天戦の攻略法と立ち回りのコツ

刑天は、九日ナインソールにおける終盤戦の象徴的なボスの一人であり、その戦闘設計は「持続的圧力型AI制御」を採用した高度な難易度を誇ります。
攻撃テンポが速く、突進・範囲攻撃・回転攻撃を組み合わせた連続コンボが特徴です。
開幕時、刑天は前方への突進から斧の振り下ろしを行うため、正面での迎撃は避け、あえて斜め前方向に回避を合わせることで後方へ回り込みます。
この際、無理に攻撃を差し込まず、振り終わりの後隙(約1.2秒間)に1から2回だけ斬りを入れるのが安定戦術です。
攻撃を続けすぎると、AIがカウンター行動に移行する確率が上がり、反撃を受けやすくなります。
刑天のフェイント攻撃は「一拍遅れ」で振り下ろす独特のタイミングを持っており、パリィを狙う際は敵の腕の引き上げ動作を見極めることが鍵です。
特に第2段階以降では、振りかぶり後に溜めエフェクトが追加され、通常の攻撃との識別が難しくなります。
ここで焦ってガード入力を早めるとミスが増えるため、あえて「半テンポ遅らせる」感覚で操作することが重要です。
また、体力が50%以下になると攻撃パターンが変化し、連続突進や二段振り上げ攻撃が追加されます。
このフェーズ移行直後は無理な攻撃を控え、モーション確認を1ループ挟むことで被弾率を大幅に減らせます。
AIの挙動はプレイヤーの距離保持傾向に応じて変化するため、一定の距離(約6メートル相当)を保ち、刑天の誘導突進を誘う立ち回りが有効です。
ビルド面では、火力特化構成よりも、スタミナ回復や回避硬直軽減の符術を優先する方が安定します。
特に「玄息符(スタミナ再生)」と「護身符(被弾時軽減)」の併用は、連戦における生存率を大きく引き上げます。
刑天の設計思想には、「プレイヤーのリズム把握能力を試す」という明確な意図が見られます。
このリズムベースAI挙動は、2024年の国際AIゲーム設計会議(AIIDE)でも研究対象として取り上げられており、反応速度と予測行動のバランスを検証する実例として分析されています。
刑天戦はその応用例の一つであり、AI戦闘デザインの完成度を体感できる好例といえます。
真エンド到達条件とルート分岐解説

九日ナインソールにおける真エンドは、単なるエンディングの一種ではなく、世界観の核心に迫る物語的到達点として設計されています。
表面上のストーリーを完結させる「通常エンド」に対し、真エンドは複数のサイドクエスト・人物イベント・アイテム収集・謎解き要素を統合的に進行させる必要があります。
そのため、すべての条件を満たすには、計画的な探索と分岐管理が欠かせません。
真エンドに必要な前提条件は大きく分けて三系統あります。
1つ目は、「印章収集」と呼ばれるメイン進行条件です。
これは全ボス撃破後に得られる九つの印章を集めることで、封印領域の最奥へ到達できるようになる要素です。
ただし、単に印章を集めるだけでは真エンドには入れません。
2つ目は、拠点内の人物イベントの完遂です。
易公や天人関連のNPCとの会話イベントを進めることで、特定の選択肢や贈呈物が解放されます。
これには、道教石窟で得られる聖典解読イベントが密接に関係しており、順序を誤ると特定の台詞や行動が発生しないことがあります。
これを防ぐために、各ボス撃破後は必ず拠点に戻り、会話内容が更新されているか確認することが推奨されます。
3つ目は、「特殊イベント・仕掛け達成系フラグ」の達成です。
具体的には、道教石窟の封印棺を全て開放し、聖典関連のギミックを完遂することで爆薬の素材を入手し、それを鍛冶師NPCに渡すと特殊武器が製作可能になります。
この武器を所持した状態で特定イベントに進むと、真エンド分岐条件の一部が発動します。
また、調合士NPCに全種の毒素材を渡し、調合完了イベントを全て達成することも条件のひとつです。
これらの条件を整理すると、真エンドルートは次のような流れで構成されています。
●全印章の回収(9箇所)
●道教石窟の聖典ギミックを全て達成
●鍛冶師・調合士・易公のイベントを全て完遂
●爆薬製作および武器完成
●拠点イベント更新後、終局エリアで選択発生
これらの要素は複合的に絡み合うため、一部を後回しにするとフラグが無効化されるケースがあります。
特に、ボス撃破直後に戻ってイベントを進めるだけでも、達成率が20から30%向上すると言われています。
開発側が公開している公式設定資料(出典:Red Candle Studio開発者コメント)によると、真エンドは「天人と人間の融合」「罪と再生」というテーマを体現しており、プレイヤーが探索の中で収集した断片的な知識をもとに最終選択を下すよう設計されています。
このため、単なる隠しルートではなく、ゲーム全体の思想を読み解くための「答え合わせ」に相当するエンディング構造といえるでしょう。
真エンド分岐を見逃さないためには、探索ごとにクエスト管理ノートを作成し、進行済みと未達成の項目を整理しておくのが有効です。
特にNPC関連の会話や渡し物イベントは、セーブデータを複数保持しながら確認することで安全に分岐条件を追跡できます。
エンディング後のトロフィー獲得要素

エンディング後の九日ナインソールは、いわば「総仕上げ」としての高難度挑戦フェーズとなります。
この段階では、ゲーム中で取り逃した実績やトロフィー要素を集中的に回収することが可能です。
まず、トロフィーの分類としては以下の3系統に大別されます。
●ストーリー関連(エンディング・イベント達成)
●戦闘関連(ノーダメージ撃破、特定技で勝利など)
●探索関連(鐘・碑文・アイテム・特定エリア達成)
特に鐘ギミックや詩碑文の関連実績は、物語上の象徴として深く結びついており、特定のエリアでしか達成できません。
鐘の順序解読系のトロフィーは、道教石窟や天人エリアで取得できる詩のフレーズと対応していることが多く、テキストを記録しておくことで再挑戦時の効率が上がります。
一方で、戦闘系の実績では「ノーダメージ撃破」や「パリィのみで勝利」など、極めて精密な操作を要求する条件が設定されています。
これらは1周目では達成が難しいため、エンディング後の装備強化状態で再挑戦するのが一般的です。
この際、火力特化よりも防御・回復特化のビルドに切り替え、敵パターンを完全に把握した上で試行回数を重ねると成功率が上がります。
さらに、探索関連のトロフィーには、特定条件を満たすことでのみ出現する隠しイベントが存在します。
例として、全鐘を正しい順序で鳴らすことで発生する「共鳴の記憶」や、特定の碑文を全て読むことで開放される「伝承を継ぐ者」などがあります。
これらはプレイヤーの行動ログに依存しており、1つでも未確認の碑文があると達成できません。
効率的なトロフィー収集を行うためには、まずストーリー進行度を基準にチェックリストを作成し、エリアごとに達成済み・未達成を整理します。
鐘や碑文の位置情報はマップ内の構造記憶と紐づくため、探索順を固定化すると見逃しが減ります。
また、こうした周回設計は、現代アクションゲームにおける「リプレイ報酬構造(Replay Incentive Design)」の典型的な実装例です。
つまり、エンディング後に再度ゲームをプレイする動機づけを提供するため、報酬構造を多層的に配置する設計思想が働いています。
これにより、単なるやり込み要素ではなく、作品全体の完成度を再体験する「再構築型エンディング体験」が形成されているのです。
エンディング後の世界は、プレイヤーの解釈力と分析力を試す最後のステージといえます。
取り逃した実績をすべて回収する過程こそが、九日ナインソールの真なる完結であり、物語とシステムの融合が最も明確に感じられる瞬間です。
【まとめ】九日ナインソールの攻略について
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。


